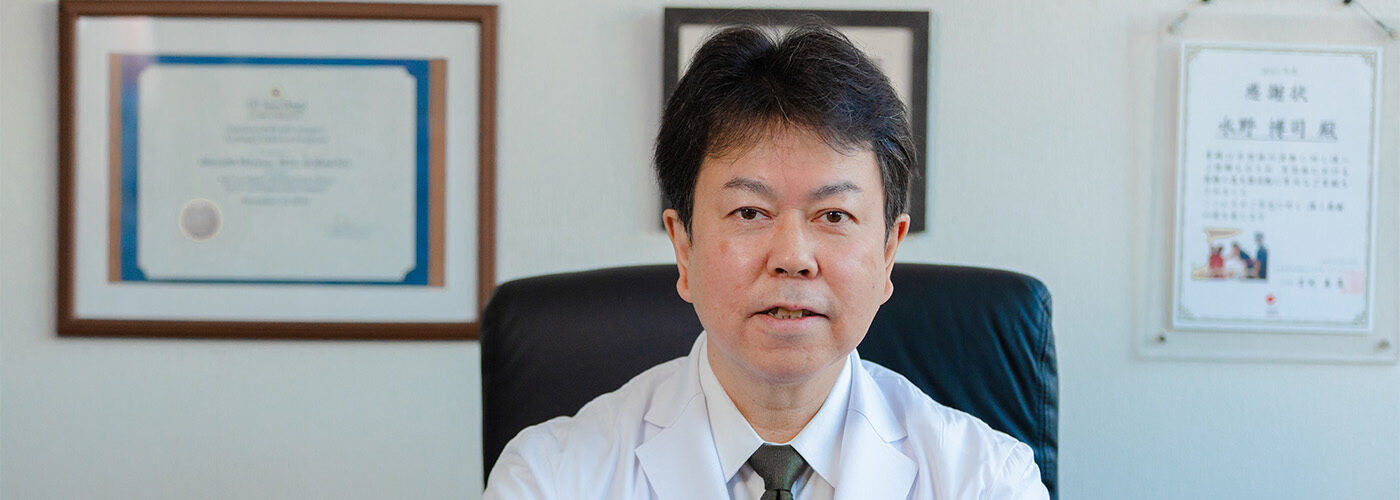防衛医大で形成外科と運命的な出会いを果たした水野教授。自衛隊関連の複数の医療機関で、12年間に渡り経験を積んだ。また、自衛隊時代に「UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)」に留学。最先端の手術を多数経験した。現在は、順天堂大学の教授として、乳房再建、小児形成外科、皮膚がん治療など形成外科疾患全般の治療に携わっている。水野教授の「スーパーポジティブ」を体現するキャリアの歩みについてお話しいただいた。

医師を目指して防衛医大に進学した水野教授。診療科選びに悩んでいる時にあるきっかけで、形成外科医の道を進む決意をした。運命的な形成外科との出会いなど、医師になるまでの道のりを振り返っていただいた。
医師という仕事を意識したきっかけは、小学生の頃に祖父から言われた「孫の中に1人くらい医者がいると良いな」という言葉です。いとこたちはたくさんいるものの、私よりも年上がほとんどで、ある程度、将来の道も決まっていたため、何となく耳に焼き付いていました。
医師になると決めたのは、高校生のときです。母校は私立の男子校で医者の子どもも多く、医学部を目指す生徒がたくさんいました。理系が得意だったこともあり、自然と医学部を目指すようになりました。
防衛医大に進学し、6年生のときに形成外科に進む決心をしました。私の診療科選びの軸は、学問的に満足できるか、経済的に独立できるか、1週間程度のまとまった休みが取れるかの3つでした。学生時代、スキューバーダイビングやスキーをしていたので、そういったことが楽しめる診療科がいいなと。しかし、3つ全てを満たす進路が見つからず、悩んでいました。
ある時、救急部の実習が1週間あり、そのうち2日間は形成外科の手術見学でした。当時の日本における形成外科は専門医も本当に少なく、形成外科医が1人もいない医学部も珍しくないほどだったんです。そのため、見学するまでは形成外科について何も知りませんでしたが、いざ手術を見ると本当に面白かったですね。働いてみると、経済面や休みについては理想とは少し違ったものの、気持ちはとても満たされています。
大学卒業後は、硫黄島の航空基地など様々な職場に赴任し、12年間にわたり自衛隊に在籍しました。
コンテンツは会員限定です。
続きをご覧になるには以下よりログインするか、会員登録をしてください。