東京大学医学部を卒業後、緑内障分野の専門家として多くの患者を診察。失明を予防し、患者の生活の質を守り続けてきた相原教授。キャリアアップよりも自分を見失わないことを重視して、医師として歩んできた。相原教授の道のりを振り返る。
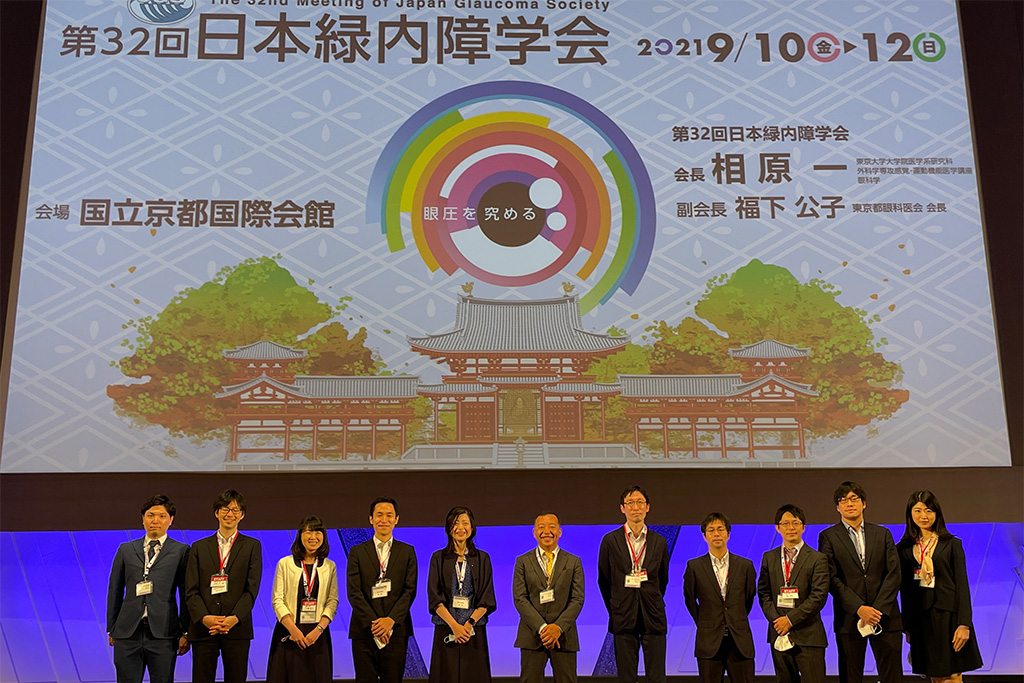
キャリアの成功体験は「日々の仕事のなかで誰かに喜んでもらうこと」という相原教授。緑内障の専門家として、患者の役に立てる喜びを噛みしめながら仕事をしている。
大きく成功するよりも、日常のなかで誰かに喜んでもらうことの積み重ねが大切だと感じています。治療が満足のいく結果となり、患者さんの役に立てるのが何より嬉しいですね。
私が医者になろうと思ったのは、小学生の頃。医師であれば、働きながら昆虫の研究ができると考えたからです。昆虫、特に蝶が好きで、幼稚園の時には自分で標本を作るほどでした。しかし、昆虫博士では食べていくのは難しいと聞き、昆虫の図鑑を書いている人の約半分は医者をしながらアマチュアで研究している人たちだと知りました。そこで、私もその道を行こうと思ったのです。その後、小学校5年生の時に、一緒に住んでいた祖母が闘病の末に亡くなり、医者を真面目に目指すことにしました。
眼科に進んだのは、私は手先が器用で解剖も好きだったこともあり、顕微鏡を使った非常に細かい手術に興味があったからです。耳鼻科の手術も興味深かったのですが、眼科は機能を再建する要素が強く、面白く感じました。眼科は手術跡のきれいさが見た目で分かるので、他の人からフィードバックがもらえるのも魅力です。また、昆虫や植物を見る・絵を描く・写真を撮る・観察するのが好きなので、観察力が必要とされる眼科であれば自分の目を活かせると考えました。
眼科のなかでも緑内障を選んだ理由は、患者さんとの付き合いが続くからです。緑内障は回復しないので、悪化しないようにケアを続けなければなりません。そのため、患者さんの生活環境や仕事など、その人の背景を知って診療します。私は人が好きなので、医学者ではなくお医者さんになりたかった。人を様々な角度から総合的に見る機会の多い緑内障は、自分に合っていると思います。
大学で勤務していた期間は長かったですが、若い人にポジションを譲るために48歳の時に辞めて、クリニックの副院長をしていた時期もありました。縁があって大学に戻りましたが、患者さんの役に立てるのであれば、ポジションにはこだわりません。
研修医時代から約30年診察を続けている患者さんが何人かいて、私にとって大きな財産だと感じています。緑内障は完治しない病気なので、亡くなるまで目が見えなくならなければ成功です。手術で回復することがないため、お礼を言われる機会は多くありません。ですが、最後まで患者さんの目が見えていれば、それで満足です。「先生に診てもらえるとホッとする」と言ってくれる患者さんもいて、とても嬉しいですね。
コンテンツは会員限定です。
続きをご覧になるには以下よりログインするか、会員登録をしてください。





