MRから医療機器営業への転職が急増!?両者の違いを解説
2022/10/03
2025/01/27
医療業界の営業職のなかでも人気の高いMRですが、MR認定センターによると、国内のMR数はピークである2013年度の6万5752人から、6年連続で減少。2019年は5万7158人にまで減りました。コンプライアンス意識の変化やデジタル化の影響により、今後も減少傾向は続くでしょう。
こうした状況を背景に、MRから医療機器営業へ転職する人が増えています。この記事では、MRと医療機器営業の違いを紹介します。今後のキャリアを考えるにあたり、ぜひ参考にしてください。
こうした状況を背景に、MRから医療機器営業へ転職する人が増えています。この記事では、MRと医療機器営業の違いを紹介します。今後のキャリアを考えるにあたり、ぜひ参考にしてください。
同じ医療業界の営業職でもここが違う!MRと医療機器営業について解説
MRと医療機器営業は、医療業界の営業職という共通点はありますが、役割などや営業スタイルなど大きく異なります。それぞれの職種について解説します。
MRは「医薬品情報担当者」とも呼ばれ、製薬会社などの社員として病院やクリニックに訪問。医師などの医療従事者に、医薬品情報を適切に提供します。情報提供を通して信頼関係を構築し、担当する医薬品を採択してもらうのがゴールです。営業職でありながら、価格の交渉は一切しないという特徴があります。
診療時間前や診療時間後、休み時間といった医師の手が空いているタイミングで面会して営業します。また、勉強会などを開催し、出席した医師に営業活動を行うこともあります。
以前は製薬会社に勤務するMRがほとんどでしたが、近年は、MRの派遣や医薬品営業・マーケティングを代行する「CSO(医薬品販売業務受託機関)」に所属し、「コントラクトMR」として働くケースが増加しています。
オンライン商談の普及などにより、常に多くのMRを雇用するのではなく、新薬発売など必要なタイミングでコントラクトMRを活用するビジネススタイルに移行しているためです。
医師に適切に医薬品情報を伝えるポジションなので、担当する医薬品だけではなく、関連する疾病をはじめとする深い専門知識が求められます。最先端の論文を読むなど、常に勉強が必要です。
MRに就職したり業務をしたりするのにあたって、国家資格のような必須の資格はありません。しかし、ほとんどのMRが「MR認定証」を取得しています。
MR認定証とは、MRに必要な知識・素質が備わっているかを客観的に評価する「MR認定試験」の合格者が取得できる証明書です。製薬会社やCSOの多くが、入社後の取得を義務付けています。
医療機関によっては、MR認定証を持っていないMRの入館を禁じているため、MRとして働くうえで実質的に欠かせない資格です。
医療機器営業とは、ペースメーカーや人工関節、MRI、ガーゼなど、診療に使用する機械や器具類を取り扱う営業職です。
医療機器営業は、基本的にルート営業です。医療機器メーカーまたは卸売業者の社員として、病院やクリニックに訪問して営業します。商談の主な相手は医師ですが、MRIなど数千万円~数億かかる高額な医療機器を営業する場合は、病院の経営層に対し営業をするケースもあります。
MRと違い直接医療機器を販売するので、価格交渉も仕事のひとつです。また、取り扱う医療機器によっては、医師などの医療従事者への使用方法のレクチャーや、手術に立ち会って緊急対応することもあります。
医療機器の知識やコミュニケーション力だけでなく、実際に機器を操作するオペレーションスキルも必要な職業です。ただし、医療知識は、MRほど高度な内容を知る必要はありません。MR認定証のような、実質的に必須となる資格もないという違いがあります。
このように、MRと医療機器営業は一見似ていますが、仕事内容は大きく異なります。MRや医療機器営業に転職する際は、しっかり確認して、自分に合った仕事を選択しましょう。
(1)MRとは
MRは「医薬品情報担当者」とも呼ばれ、製薬会社などの社員として病院やクリニックに訪問。医師などの医療従事者に、医薬品情報を適切に提供します。情報提供を通して信頼関係を構築し、担当する医薬品を採択してもらうのがゴールです。営業職でありながら、価格の交渉は一切しないという特徴があります。
診療時間前や診療時間後、休み時間といった医師の手が空いているタイミングで面会して営業します。また、勉強会などを開催し、出席した医師に営業活動を行うこともあります。
以前は製薬会社に勤務するMRがほとんどでしたが、近年は、MRの派遣や医薬品営業・マーケティングを代行する「CSO(医薬品販売業務受託機関)」に所属し、「コントラクトMR」として働くケースが増加しています。
オンライン商談の普及などにより、常に多くのMRを雇用するのではなく、新薬発売など必要なタイミングでコントラクトMRを活用するビジネススタイルに移行しているためです。
医師に適切に医薬品情報を伝えるポジションなので、担当する医薬品だけではなく、関連する疾病をはじめとする深い専門知識が求められます。最先端の論文を読むなど、常に勉強が必要です。
MRに就職したり業務をしたりするのにあたって、国家資格のような必須の資格はありません。しかし、ほとんどのMRが「MR認定証」を取得しています。
MR認定証とは、MRに必要な知識・素質が備わっているかを客観的に評価する「MR認定試験」の合格者が取得できる証明書です。製薬会社やCSOの多くが、入社後の取得を義務付けています。
医療機関によっては、MR認定証を持っていないMRの入館を禁じているため、MRとして働くうえで実質的に欠かせない資格です。
(2)医療機器営業とは
医療機器営業とは、ペースメーカーや人工関節、MRI、ガーゼなど、診療に使用する機械や器具類を取り扱う営業職です。
医療機器営業は、基本的にルート営業です。医療機器メーカーまたは卸売業者の社員として、病院やクリニックに訪問して営業します。商談の主な相手は医師ですが、MRIなど数千万円~数億かかる高額な医療機器を営業する場合は、病院の経営層に対し営業をするケースもあります。
MRと違い直接医療機器を販売するので、価格交渉も仕事のひとつです。また、取り扱う医療機器によっては、医師などの医療従事者への使用方法のレクチャーや、手術に立ち会って緊急対応することもあります。
医療機器の知識やコミュニケーション力だけでなく、実際に機器を操作するオペレーションスキルも必要な職業です。ただし、医療知識は、MRほど高度な内容を知る必要はありません。MR認定証のような、実質的に必須となる資格もないという違いがあります。
このように、MRと医療機器営業は一見似ていますが、仕事内容は大きく異なります。MRや医療機器営業に転職する際は、しっかり確認して、自分に合った仕事を選択しましょう。
MRから医療機器営業へ転職するなら必見!医療機器の種類とは
会社によって取り扱う医療機器が異なるので、医療機器営業に転職する際は、医療機器について知っておくことが大切です。代表的な製品について種類ごとに解説します。
治療機器とは、カテーテル・心臓ペースメーカーなど、治療に使用する医療機器を指します。患者の身体に埋め込んで使用するものも多く、製品の提案だけではなく、使い方のレクチャーや手術の立ち合いなども重要な仕事です。
人工心肺装置や人工呼吸器などを担当する場合は、医師だけではなく看護師・臨床工学技士にも使用方法を説明する機会があります。
トラブル対応が発生することも多いため、製品知識をしっかり身に着けるとともに、冷静かつ的確に対応できるよう、スキルを磨きましょう。
大変な面もありますが、自分が担当している製品が実際に使われている現場に立ち会えたり、医師たちから感謝の言葉をもらえたりと、やりがいを感じる場面が多い商材です。
日本の治療機器メーカーは競争力が弱いといわれており、外資系メーカーの製品の輸入に頼っている面があります。治療機器を担当したい場合は、外資系メーカーへの転職も視野に入れるのをおすすめします。
大型診断機器とは、MRIやCTなど患者の身体を診断するための検査に使う大型の医療機器のことです。一台あたり数億~数十億円する非常に高額な製品がほとんどです。
そのため、主な商談相手は医療機関の経営陣で、予算や経営戦略にまで踏み込んだコンサルティング的な要素の強い営業スタイルで仕事をします。
非常に高額なため、商談が成立するまでに時間がかかり、すぐに成果が出ないという特徴があります。モチベーションを保ちにくい面もありますが、商談が成立した時の達成感は非常に大きいでしょう。ノルマに関しては年に1台程度とそこまでハードルは高くありません。
治療器機器とは異なり、日本の競争力が高い分野です。
患者から採取した血液・尿をはじめとする検体を検査するための診断機器です。検査キットや試薬、容器などさまざまな種類のものがあります。
営業先は医療機関よりも、大学・各種検査機関などが多い傾向にあります。商談相手は、医師や臨床検査技師がメインです。
検査キットや診断薬など消耗品を多く取り扱うため、継続した購入が期待でき、売上が安定している商材です。ルート営業の要素が強く、こまめに顔を出して商品の補充や医療現場の課題をヒアリングすることが大切です。
治療機器や大型診断機器と比べ、生命に直結する医療機器ではなく、トラブルもあまり起きません。緊急対応や手術の立ち合いはほぼ発生しないため、ワークバランスが取りやすく、プレッシャーも少なめです。
「ハードワークは避けたい」「ストレスの少ない仕事をしたい」という方には、おすすめの商材です。
マスク・点滴・手袋など医療現場で使われる消耗品のことです。在庫確認をするために定期的に医療機関を訪問します。ルート営業がメインで、すでに取引のある病院・クリニックなどに、医療用消耗品を提案することが仕事です。
医療機関で使われる医療用消耗品は、安全面・コスト・使いやすさといった点を重視して検討されます。
医師だけではなく看護師などからも、医療用消耗品に関する相談を受けるポジションです。日頃から信頼関係を築き、ニーズをしっかりヒアリングして提案することが大切です。
小型診断機器と同じく、手術の立ち会いや緊急対応はほぼありません。その代わり、こまめな対応を継続的に行う必要があり、マメなタイプの人に向いています。
(1)治療機器
治療機器とは、カテーテル・心臓ペースメーカーなど、治療に使用する医療機器を指します。患者の身体に埋め込んで使用するものも多く、製品の提案だけではなく、使い方のレクチャーや手術の立ち合いなども重要な仕事です。
人工心肺装置や人工呼吸器などを担当する場合は、医師だけではなく看護師・臨床工学技士にも使用方法を説明する機会があります。
トラブル対応が発生することも多いため、製品知識をしっかり身に着けるとともに、冷静かつ的確に対応できるよう、スキルを磨きましょう。
大変な面もありますが、自分が担当している製品が実際に使われている現場に立ち会えたり、医師たちから感謝の言葉をもらえたりと、やりがいを感じる場面が多い商材です。
日本の治療機器メーカーは競争力が弱いといわれており、外資系メーカーの製品の輸入に頼っている面があります。治療機器を担当したい場合は、外資系メーカーへの転職も視野に入れるのをおすすめします。
(2)大型診断機器
大型診断機器とは、MRIやCTなど患者の身体を診断するための検査に使う大型の医療機器のことです。一台あたり数億~数十億円する非常に高額な製品がほとんどです。
そのため、主な商談相手は医療機関の経営陣で、予算や経営戦略にまで踏み込んだコンサルティング的な要素の強い営業スタイルで仕事をします。
非常に高額なため、商談が成立するまでに時間がかかり、すぐに成果が出ないという特徴があります。モチベーションを保ちにくい面もありますが、商談が成立した時の達成感は非常に大きいでしょう。ノルマに関しては年に1台程度とそこまでハードルは高くありません。
治療器機器とは異なり、日本の競争力が高い分野です。
(3)小型診断機器
患者から採取した血液・尿をはじめとする検体を検査するための診断機器です。検査キットや試薬、容器などさまざまな種類のものがあります。
営業先は医療機関よりも、大学・各種検査機関などが多い傾向にあります。商談相手は、医師や臨床検査技師がメインです。
検査キットや診断薬など消耗品を多く取り扱うため、継続した購入が期待でき、売上が安定している商材です。ルート営業の要素が強く、こまめに顔を出して商品の補充や医療現場の課題をヒアリングすることが大切です。
治療機器や大型診断機器と比べ、生命に直結する医療機器ではなく、トラブルもあまり起きません。緊急対応や手術の立ち合いはほぼ発生しないため、ワークバランスが取りやすく、プレッシャーも少なめです。
「ハードワークは避けたい」「ストレスの少ない仕事をしたい」という方には、おすすめの商材です。
(4)医療用消耗品
マスク・点滴・手袋など医療現場で使われる消耗品のことです。在庫確認をするために定期的に医療機関を訪問します。ルート営業がメインで、すでに取引のある病院・クリニックなどに、医療用消耗品を提案することが仕事です。
医療機関で使われる医療用消耗品は、安全面・コスト・使いやすさといった点を重視して検討されます。
医師だけではなく看護師などからも、医療用消耗品に関する相談を受けるポジションです。日頃から信頼関係を築き、ニーズをしっかりヒアリングして提案することが大切です。
小型診断機器と同じく、手術の立ち会いや緊急対応はほぼありません。その代わり、こまめな対応を継続的に行う必要があり、マメなタイプの人に向いています。
MRから医療機器営業に転職するメリットって?5つのポイントを解説
MRから医療機器営業に転職する人は増えていますが、どのようなメリットがあるのでしょうか。主な5つのポイントについて、解説します。
MRも医師をサポートする営業職ですが、医療機器営業の方がより深く医師のパートナーとして関わり、寄り添ったサポートが可能です。
医師と面会するときもただ製品を紹介するのではなく「患者さんのためにどういった製品がいいのか」「よりよい医療とは何か」をじっくり話し合います。MRと比べて提案要素が大きく、そこに面白さがあります。
取り扱う医療機器によっては、手術に立ち会うこともあるため、より医師との関係が密になりやすいのが特徴です。手術が無事に終わり、安心した医師の顔を見ると役に立てているという実感が持てる。実際に医師が患者と向き合っているところを見られる。といったMRにはないやりがいを感じられます。
また、医師との関係性が深い分、MRと比較するとアポイントメントが取りやすいのもメリットです。
会社によっては、幅広いジャンルの医療機器を取り扱っているため、さまざまな製品の営業に携わるチャンスがあります。製品のジャンルや価格帯によって、商談相手や営業手法が異なるので、営業スキルを伸ばすことが可能です。
さまざまな営業スキルを身につけるのは大変ですが、その分、営業職として成長でき、よりよいキャリア形成につながります。営業スキルの向上は、給与や待遇のアップ、やりがいに直結しますし、将来的に転職する際にも有利に働きます。
キャリアアップを希望する人には、適した職業といえるでしょう。
MRは外資系企業の一部を除き、ほとんどの製薬会社で3~5年ごとに転勤があります。特に、子どものいる家庭や共働きの家庭では、転勤は大きなネックです。
医療機器営業は、転勤のない会社も多いため、転勤したくないMRは医療機器営業に転職するのもひとつの方法です。
MR数は年々減少しており、今後もその傾向は続くといわれています。さらに、デジタル化の影響や後発医薬品の台頭などにより、減少傾向に拍車がかかる可能性もあるでしょう。事実、新卒採用を控え、早期退職がスタートしている製薬会社も多数あります。
医療機器営業は、高齢化や病気の早期発見・予防のニーズ増加などを背景に成長中。日本の医療機器市場は、年3%程度の拡大を続けています。
さらに、医療機器営業の場合、機器の使い方の提案やオペレーションのレクチャーなども行うため、デジタル化が難しく、安定した雇用が期待できます。
MRは営業職の一種ですが、他の営業職とは異なる部分が多い職種です。医薬品情報担当者という言葉通り、医薬品に関する情報を医療従事者に伝える仕事なので、一般的な営業職では担当業務である価格交渉・受注・納品・代金回収などには携わりません。
また、新薬など取り扱う医薬品によっては、競合が少ないケースもあります。そのため、営業スキルよりも、医師へわかりやすく説明したり説得したりする力の方が求められる場合も多いでしょう。
医療機器営業は、一般的な営業職と同じように価格交渉・受注・納品・代金回収なども担当します。
営業職としてスキルを磨きたい場合は、MRよりも医療機器営業の方が適しているといえます。
(1)医師のパートナーとして寄り添った営業ができる
MRも医師をサポートする営業職ですが、医療機器営業の方がより深く医師のパートナーとして関わり、寄り添ったサポートが可能です。
医師と面会するときもただ製品を紹介するのではなく「患者さんのためにどういった製品がいいのか」「よりよい医療とは何か」をじっくり話し合います。MRと比べて提案要素が大きく、そこに面白さがあります。
取り扱う医療機器によっては、手術に立ち会うこともあるため、より医師との関係が密になりやすいのが特徴です。手術が無事に終わり、安心した医師の顔を見ると役に立てているという実感が持てる。実際に医師が患者と向き合っているところを見られる。といったMRにはないやりがいを感じられます。
また、医師との関係性が深い分、MRと比較するとアポイントメントが取りやすいのもメリットです。
(2)さまざまな営業スキルを身につけられる
会社によっては、幅広いジャンルの医療機器を取り扱っているため、さまざまな製品の営業に携わるチャンスがあります。製品のジャンルや価格帯によって、商談相手や営業手法が異なるので、営業スキルを伸ばすことが可能です。
さまざまな営業スキルを身につけるのは大変ですが、その分、営業職として成長でき、よりよいキャリア形成につながります。営業スキルの向上は、給与や待遇のアップ、やりがいに直結しますし、将来的に転職する際にも有利に働きます。
キャリアアップを希望する人には、適した職業といえるでしょう。
(3)転勤の可能性が低い
MRは外資系企業の一部を除き、ほとんどの製薬会社で3~5年ごとに転勤があります。特に、子どものいる家庭や共働きの家庭では、転勤は大きなネックです。
医療機器営業は、転勤のない会社も多いため、転勤したくないMRは医療機器営業に転職するのもひとつの方法です。
(4)雇用の安定性・将来性が高い
MR数は年々減少しており、今後もその傾向は続くといわれています。さらに、デジタル化の影響や後発医薬品の台頭などにより、減少傾向に拍車がかかる可能性もあるでしょう。事実、新卒採用を控え、早期退職がスタートしている製薬会社も多数あります。
医療機器営業は、高齢化や病気の早期発見・予防のニーズ増加などを背景に成長中。日本の医療機器市場は、年3%程度の拡大を続けています。
さらに、医療機器営業の場合、機器の使い方の提案やオペレーションのレクチャーなども行うため、デジタル化が難しく、安定した雇用が期待できます。
(5)より営業らしい仕事ができる
MRは営業職の一種ですが、他の営業職とは異なる部分が多い職種です。医薬品情報担当者という言葉通り、医薬品に関する情報を医療従事者に伝える仕事なので、一般的な営業職では担当業務である価格交渉・受注・納品・代金回収などには携わりません。
また、新薬など取り扱う医薬品によっては、競合が少ないケースもあります。そのため、営業スキルよりも、医師へわかりやすく説明したり説得したりする力の方が求められる場合も多いでしょう。
医療機器営業は、一般的な営業職と同じように価格交渉・受注・納品・代金回収なども担当します。
営業職としてスキルを磨きたい場合は、MRよりも医療機器営業の方が適しているといえます。
MRから医療機器営業に転職するデメリットって?4つのポイントを解説
MRから医療機器営業への転職には、デメリットもあります。主なデメリットを4つ解説しますので、転職の際の参考にしてください。
大手転職サイト『doda』が2023年に発表した職種分類別の平均年収ランキング※1によると、MRの平均年収が732万円なのに対し、医療機器メーカーの営業職は527万円と200万円以上の差があります。
とはいえ、営業系職種全体の平均年収は456万円なので、他業界に比べると年収は高めです。また、営業成績や会社の業績によっては、さらに多くの年収が見込めます。
※1 『doda』平均年収ランキング(平均年収/生涯賃金)【最新版】
医療機器営業は、取り扱う製品によって営業スタイルや忙しさなどが大きく異なるケースがあります。幅広い営業スキルを身につけられる反面、好成績を収めていた人でも、製品が変わることで上手くいかなくなる可能性もあるのです。
また、手術の立ち合いや使用方法のレクチャーなど、一般的な営業職には必要のないスキルを求められるのも、人によってはネックとなるでしょう。
特に血を見るのが苦手な場合、手術の立ち合いが必要な医療機器を担当するのは難しいので、転職前によく確認してください。
医療機器営業は、MRに比べると転勤の可能性は低いです。しかし、一人ひとりの担当区域が広く、営業職の人数が少ないため、出張が発生するケースがあります。
検査機器や手術に使用する機器など取り扱う商材によっては、不具合があると診療が進まず、夜間・休日の緊急対応を求められる可能性があります。
そのため、ハードワークになりやすく、ワークライフバランスはやや取りにくいかもしれません。
また、緊急対応が必要な状況では、医師や看護師などの医療従事者がピリピリしており、プレッシャーがかかります。
夜間・休日の緊急対応が難しい場合は、取り扱う商材や会社の勤務体系などをしっかり確認してから転職先を選びましょう。
(1)MRと比べ年収が低め
大手転職サイト『doda』が2023年に発表した職種分類別の平均年収ランキング※1によると、MRの平均年収が732万円なのに対し、医療機器メーカーの営業職は527万円と200万円以上の差があります。
とはいえ、営業系職種全体の平均年収は456万円なので、他業界に比べると年収は高めです。また、営業成績や会社の業績によっては、さらに多くの年収が見込めます。
※1 『doda』平均年収ランキング(平均年収/生涯賃金)【最新版】
(2)取り扱う製品との相性が悪い場合がある
医療機器営業は、取り扱う製品によって営業スタイルや忙しさなどが大きく異なるケースがあります。幅広い営業スキルを身につけられる反面、好成績を収めていた人でも、製品が変わることで上手くいかなくなる可能性もあるのです。
また、手術の立ち合いや使用方法のレクチャーなど、一般的な営業職には必要のないスキルを求められるのも、人によってはネックとなるでしょう。
特に血を見るのが苦手な場合、手術の立ち合いが必要な医療機器を担当するのは難しいので、転職前によく確認してください。
(3)出張が発生する場合がある
医療機器営業は、MRに比べると転勤の可能性は低いです。しかし、一人ひとりの担当区域が広く、営業職の人数が少ないため、出張が発生するケースがあります。
(4)夜間や休日に緊急対応が必要なケースがある
検査機器や手術に使用する機器など取り扱う商材によっては、不具合があると診療が進まず、夜間・休日の緊急対応を求められる可能性があります。
そのため、ハードワークになりやすく、ワークライフバランスはやや取りにくいかもしれません。
また、緊急対応が必要な状況では、医師や看護師などの医療従事者がピリピリしており、プレッシャーがかかります。
夜間・休日の緊急対応が難しい場合は、取り扱う商材や会社の勤務体系などをしっかり確認してから転職先を選びましょう。
MRから医療機器営業への転職に成功するには準備が大切!
MRは医療・医療業界に関する知見や営業経験があるため、医療機器営業への転職において有利です。
しかし、未経験職種へのキャリアチェンジのため、しっかり対策が必要です。特に有名企業や条件の良い求人の場合は競争率が高く、ハードルが高いので注意しましょう。
MRとしての経験・スキルを棚卸しして、転職先でどのように活かすのか考え、応募書類や面接での受け答えで的確に伝える必要があります。
初めて転職する場合や効率的に転職活動を進めたい場合は、医療業界に特化した転職エージェントの利用がおすすめです。
MRから医療機器営業へのキャリアチェンジに携わったキャリアアドバイザーが多く、的確なアドバイスをもらえます。プロによる応募書類の添削や面接練習を受けることで、採用担当から高く評価されるようになり、スムーズに内定を獲得できる可能性が高まります。
また、一般の求人サイトには掲載されていない「非公開求人」やその転職エージェントでしか募集していない「独占求人」を紹介してもらえる可能性があり、チャンスを増やせるのも大きなメリットです。
ほとんどの転職エージェントは無料で利用できるので、MRから医療機器営業への転職に興味がある方は、まずは転職エージェントに相談してみましょう。
しかし、未経験職種へのキャリアチェンジのため、しっかり対策が必要です。特に有名企業や条件の良い求人の場合は競争率が高く、ハードルが高いので注意しましょう。
MRとしての経験・スキルを棚卸しして、転職先でどのように活かすのか考え、応募書類や面接での受け答えで的確に伝える必要があります。
初めて転職する場合や効率的に転職活動を進めたい場合は、医療業界に特化した転職エージェントの利用がおすすめです。
MRから医療機器営業へのキャリアチェンジに携わったキャリアアドバイザーが多く、的確なアドバイスをもらえます。プロによる応募書類の添削や面接練習を受けることで、採用担当から高く評価されるようになり、スムーズに内定を獲得できる可能性が高まります。
また、一般の求人サイトには掲載されていない「非公開求人」やその転職エージェントでしか募集していない「独占求人」を紹介してもらえる可能性があり、チャンスを増やせるのも大きなメリットです。
ほとんどの転職エージェントは無料で利用できるので、MRから医療機器営業への転職に興味がある方は、まずは転職エージェントに相談してみましょう。
まとめ
MRと医療機器営業は、同じ医療業界の営業職であり、一見すると似ている職業ではありますが、仕事内容など大きな違いがあります。
医療機器営業の仕事内容は、医療機器の種類によって異なるので、転職活動をスタートする前にチェックしておきましょう。
MR数の減少に伴い、医療機器営業に転職する人は増加しています。MRから医療機器営業に転職するメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
・医師のパートナーとして寄り添った営業ができる
・さまざまな営業スキルを身につけられる
・転勤の可能性が低い
・雇用の安定性・将来性が高い
<デメリット>
・MRと比べ年収が低め
・取り扱う製品との相性が悪い場合がある
・出張が発生する場合がある
もし転職するのなら、メリット・デメリットをしっかり把握したうえで検討しましょう。
医療機器営業に転職する際は、医療業界専門の転職サイトや転職エージェントを使うのがおすすめです。一般的な転職サイトにも求人は掲載されていますが、専門サイトならではの求人や、より実情に沿った情報などを手に入れられるでしょう。
医療機器営業の仕事内容は、医療機器の種類によって異なるので、転職活動をスタートする前にチェックしておきましょう。
MR数の減少に伴い、医療機器営業に転職する人は増加しています。MRから医療機器営業に転職するメリット・デメリットは以下の通りです。
<メリット>
・医師のパートナーとして寄り添った営業ができる
・さまざまな営業スキルを身につけられる
・転勤の可能性が低い
・雇用の安定性・将来性が高い
<デメリット>
・MRと比べ年収が低め
・取り扱う製品との相性が悪い場合がある
・出張が発生する場合がある
もし転職するのなら、メリット・デメリットをしっかり把握したうえで検討しましょう。
医療機器営業に転職する際は、医療業界専門の転職サイトや転職エージェントを使うのがおすすめです。一般的な転職サイトにも求人は掲載されていますが、専門サイトならではの求人や、より実情に沿った情報などを手に入れられるでしょう。
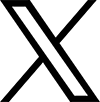
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
