医療機器のクラス分類のルールって?米国や欧州の制度も解説
2025/04/04
2025/04/10
医療機器業界で働く方にとって、各国の医療機器クラス分類のルールを理解することは、非常に重要です。
この記事では、日本の医療機器クラス分類のルールと、米国や欧州における制度、クラス分類が製品認可プロセスにどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。グローバルに活動する医療機器メーカーや国際的な薬事規制に携わる方にとって、実務に役立つ内容をまとめました。
この記事では、日本の医療機器クラス分類のルールと、米国や欧州における制度、クラス分類が製品認可プロセスにどのような影響を与えるのかを詳しく解説します。グローバルに活動する医療機器メーカーや国際的な薬事規制に携わる方にとって、実務に役立つ内容をまとめました。
医療機器クラス分類とはそもそもどんなもの?わかりやすく解説
医療機器は、人間の身体に直接作用し、生命や健康に大きな影響を与える製品です。日本では、医療機器の有効性と安全性を担保するため、医療機器を薬機法に基づき、「一般医療機器」「管理医療機器」「高度管理医療機器」の3つに分類しています。
さらに国際的な基準である「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」で定められた分類ルールを参考に、不具合が出た場合に人体に及ぼすリスクの大きさ別に「クラスⅠ~Ⅳ」の4つのクラスに分類しています。
大きなリスクを伴う医療機器ほど高いクラスに分類され、製造・販売などもより厳密に規制されているので注意が必要です。
米国や欧州など他の国でも日本と同じく、医療機器規制国際整合化会合で定められた分類ルールを参考に、医療機器をリスクの大きさで分類しています。しかし、具体的な分類基準など制度の詳細は異なります。
さらに国際的な基準である「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」で定められた分類ルールを参考に、不具合が出た場合に人体に及ぼすリスクの大きさ別に「クラスⅠ~Ⅳ」の4つのクラスに分類しています。
大きなリスクを伴う医療機器ほど高いクラスに分類され、製造・販売などもより厳密に規制されているので注意が必要です。
米国や欧州など他の国でも日本と同じく、医療機器規制国際整合化会合で定められた分類ルールを参考に、医療機器をリスクの大きさで分類しています。しかし、具体的な分類基準など制度の詳細は異なります。
日本の医療機器クラス分類のルールって?具体的例とともに解説
日本において医療機器は、以下の4つのクラスに分類されています。それぞれの概要と医療機器例を紹介します。
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
体外診断用機器・X線フィルム・聴診器・水銀柱式血圧計・縫合針など
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
画像診断機器・造影剤注入装置・電子体温計・電子式血圧計・電子内視鏡など
不具合が生じた場合に、人体へのリスクが比較的高いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
中空糸型透析器・人工関節・人工骨インプラント・人工呼吸器・角膜矯正用コンタクトレンズなど
不具合が生じた場合に、人体へのリスクが高く、生命の危険に直結する可能性のある医療機器です。
<医療機器例>
植込み型ペースメーカー・人工心臓弁・冠動脈用ステント・人工皮膚・吸収性縫合糸など
(1)クラスⅠ(一般医療機器)
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
体外診断用機器・X線フィルム・聴診器・水銀柱式血圧計・縫合針など
(2)クラスⅡ(管理医療機器)
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
画像診断機器・造影剤注入装置・電子体温計・電子式血圧計・電子内視鏡など
(3)クラスⅢ(高度管理医療機器)
不具合が生じた場合に、人体へのリスクが比較的高いと考えられる医療機器です。
<医療機器例>
中空糸型透析器・人工関節・人工骨インプラント・人工呼吸器・角膜矯正用コンタクトレンズなど
(4)クラスⅣ(高度管理医療機器)
不具合が生じた場合に、人体へのリスクが高く、生命の危険に直結する可能性のある医療機器です。
<医療機器例>
植込み型ペースメーカー・人工心臓弁・冠動脈用ステント・人工皮膚・吸収性縫合糸など
医療機器のクラス分類と製造・販売のルールの関係について解説
日本では、医療機器のクラス分類によって製造・販売に関するルールが決まります。そのため、クラス分類が異なると、規制の厳しさや製造・販売ができるようになるまでの期間なども異なります。
医療機器関連の仕事をするのであれば、医療機器のクラス別のルールを知っておくのをおすすめします。
一般医療機器は、人間の身体に対するリスクが非常に低いため、製造・販売にあたってのルールもゆるやかです。
医療機器の承認審査を行うPMD(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)へ届け出れば、製造・販売できます。PMDAによる審査はありません。そのため、比較的短期間で販売をスタートできます。
管理医療機器は、不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられています。
管理医療機器のうち、厚生労働大臣が認証基準を定めたものについては、大臣の承認は不要です。民間の第三者認証機関によって、基準を満たしているかを認証します。クラスⅠとは異なり、承認を取得するまである程度の時間がかかります。
ただし認証基準に適合しない場合は、厚生労働大臣の承認を得る必要があります。厚生労働省に申請し、PMDAが審査を実施します。
クラスⅢ・クラスⅣは、人体へのリスクが高いため、製造・販売にあたって厚生労働大臣の承認が必要です。承認の審査は、PMDAが実施します。
ただし、クラスⅢの医療機器のうち、認証基準のあるものについては、クラスⅡと同じく、第三者認証機関による認証が可能です。
承認申請には、臨床試験データを含む詳細な資料の提出が求められ、申請から承認まで早くても半年はかかります。書類などに不備があると再審査の対象となり、さらに長い時間がかかります。
このようにクラス分類が上がるほど、承認までのプロセスが厳しく、市場投入までのコスト、時間、必要な人的リソースが増加します。
そのため医療機器メーカーでは、製品開発の初期段階からクラス分類に合わせた戦略立案が欠かせません。
医療機器関連の仕事をするのであれば、医療機器のクラス別のルールを知っておくのをおすすめします。
(1)クラスⅠ(一般医療機器)
一般医療機器は、人間の身体に対するリスクが非常に低いため、製造・販売にあたってのルールもゆるやかです。
医療機器の承認審査を行うPMD(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)へ届け出れば、製造・販売できます。PMDAによる審査はありません。そのため、比較的短期間で販売をスタートできます。
(2)クラスⅡ(管理医療機器)
管理医療機器は、不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられています。
管理医療機器のうち、厚生労働大臣が認証基準を定めたものについては、大臣の承認は不要です。民間の第三者認証機関によって、基準を満たしているかを認証します。クラスⅠとは異なり、承認を取得するまである程度の時間がかかります。
ただし認証基準に適合しない場合は、厚生労働大臣の承認を得る必要があります。厚生労働省に申請し、PMDAが審査を実施します。
(3)クラスⅢ・クラスⅣ(高度管理医療機器)
クラスⅢ・クラスⅣは、人体へのリスクが高いため、製造・販売にあたって厚生労働大臣の承認が必要です。承認の審査は、PMDAが実施します。
ただし、クラスⅢの医療機器のうち、認証基準のあるものについては、クラスⅡと同じく、第三者認証機関による認証が可能です。
承認申請には、臨床試験データを含む詳細な資料の提出が求められ、申請から承認まで早くても半年はかかります。書類などに不備があると再審査の対象となり、さらに長い時間がかかります。
このようにクラス分類が上がるほど、承認までのプロセスが厳しく、市場投入までのコスト、時間、必要な人的リソースが増加します。
そのため医療機器メーカーでは、製品開発の初期段階からクラス分類に合わせた戦略立案が欠かせません。
米国の医療機器クラス分類ってどうなの?基礎知識を解説
米国では、米国食品医薬品局(FDA)が医療機器を規制しており、患者やユーザーに対するリスクの大きさに応じて、3つのクラスに分類しています。
一般的にリスクが低い医療機器で、多くのものは可動部分がなく、単純な構造をしています。市販の医療機器のうち約30%がクラスⅠに該当するといわれています。
一般的な規制のみで、特別な規制はありません。FDAによる審査がなく、自分で確認して登録します。
510(k)申請と呼ばれる、新製品が既に市場に出ている実質的に同等の機器と同レベルの安全性と有効性を持つことを証明するプロセスが必要な場合もあります。
<医療機器例>
包帯・手袋・絆創膏・手動式歯ブラシなど
中程度のリスクがあり、構造は複雑ですが、不具合が発生してもすぐに重大な危険を引き起こす可能性は低い医療機器です。医療機器全体の43%を占めます。
一般的な規制だけでは安全性や有効性を確保できず、ほとんどの場合、510(k)申請が必要です。
もし比較する医療機器がない場合は、De Novo申請を行い、FDAと協議をしながら数年間掛けて、承認を進めます。
<医療機器例>
電動車椅子・輸液ポンプ・麻酔装置・心臓モニターなど
高リスクの医療機器で、生命維持などに用いられる埋め込み機器です。不具合が起きると、生命や健康に重大な影響を及ぼします。医療機器全体の10%以下が、クラスⅢに該当すると考えられます。
安全性や有効性を保障するために、多くのケースで市販前承認(PMA)が必要です。製品だけではなく、製造工程の確認などのプロセスが必要であり、承認まで時間がかかります。
<医療機器例>
人工心臓弁・ペースメーカー・人工臓器・心肺装置など
(1)クラスⅠ
一般的にリスクが低い医療機器で、多くのものは可動部分がなく、単純な構造をしています。市販の医療機器のうち約30%がクラスⅠに該当するといわれています。
一般的な規制のみで、特別な規制はありません。FDAによる審査がなく、自分で確認して登録します。
510(k)申請と呼ばれる、新製品が既に市場に出ている実質的に同等の機器と同レベルの安全性と有効性を持つことを証明するプロセスが必要な場合もあります。
<医療機器例>
包帯・手袋・絆創膏・手動式歯ブラシなど
(2)クラスⅡ
中程度のリスクがあり、構造は複雑ですが、不具合が発生してもすぐに重大な危険を引き起こす可能性は低い医療機器です。医療機器全体の43%を占めます。
一般的な規制だけでは安全性や有効性を確保できず、ほとんどの場合、510(k)申請が必要です。
もし比較する医療機器がない場合は、De Novo申請を行い、FDAと協議をしながら数年間掛けて、承認を進めます。
<医療機器例>
電動車椅子・輸液ポンプ・麻酔装置・心臓モニターなど
(3)クラスⅢ
高リスクの医療機器で、生命維持などに用いられる埋め込み機器です。不具合が起きると、生命や健康に重大な影響を及ぼします。医療機器全体の10%以下が、クラスⅢに該当すると考えられます。
安全性や有効性を保障するために、多くのケースで市販前承認(PMA)が必要です。製品だけではなく、製造工程の確認などのプロセスが必要であり、承認まで時間がかかります。
<医療機器例>
人工心臓弁・ペースメーカー・人工臓器・心肺装置など
欧州の医療機器クラス分類ってどうなの?基礎知識を解説
欧州の医療機器クラス分類は、欧州医療機器規則 (MDR)に基づいて行われており、大きく4種類に分かれます。日本や米国と同じく、リスクが高いクラスの医療機器ほど、厳しいルールが設けられています。
クラスⅠは、最も人体に対するリスクが少ない分類です。クラスⅠはさらに、人体との接触が少なく長時間にわたらない医療機器と、リスクは少ないものの滅菌指定がある、または計測機能を備えた医療機器に分かれます。
<医療機器例>
メガネのフレーム・歩行用の杖・聴診器・体温計・血圧計など
リスクは中程度で、試用期間が短いまたは断続的な製品です。侵襲度は大きくありません。
<医療機器例>
カテーテル・内視鏡・輸血用機器・注射器・外科用器具(1回のみ使用)など
中程度のリスクがあり、人間の身体の全ての組織に影響を与える可能性があります。長期にわたり使用し、クラスⅡaよりも高リスクな医療機器です。
<医療機器例>
患者モニター・レントゲン装置・人工呼吸器・人工透析器・保育器など
リスクが高く、人間の身体の機能を侵害する可能性があります。
<医療機器例>
埋め込み式心臓ペースメーカー・人工血管・中枢神経系や中枢循環器系に使用するカテーテルなど
(1)クラスⅠ
クラスⅠは、最も人体に対するリスクが少ない分類です。クラスⅠはさらに、人体との接触が少なく長時間にわたらない医療機器と、リスクは少ないものの滅菌指定がある、または計測機能を備えた医療機器に分かれます。
<医療機器例>
メガネのフレーム・歩行用の杖・聴診器・体温計・血圧計など
(2)クラスⅡa
リスクは中程度で、試用期間が短いまたは断続的な製品です。侵襲度は大きくありません。
<医療機器例>
カテーテル・内視鏡・輸血用機器・注射器・外科用器具(1回のみ使用)など
(3)クラスⅡb
中程度のリスクがあり、人間の身体の全ての組織に影響を与える可能性があります。長期にわたり使用し、クラスⅡaよりも高リスクな医療機器です。
<医療機器例>
患者モニター・レントゲン装置・人工呼吸器・人工透析器・保育器など
(4)クラスⅢ
リスクが高く、人間の身体の機能を侵害する可能性があります。
<医療機器例>
埋め込み式心臓ペースメーカー・人工血管・中枢神経系や中枢循環器系に使用するカテーテルなど
まとめ
医療機器のクラス分類は、患者・使用者へのリスクに基づいて設定され、分類によって求められる規制要件が大きく異なります。日本や米国、欧州など国や地域によって独自の分類システムがあり、同じ医療機器でも地域によって分類や申請プロセスが異なる場合があります。
グローバルに展開する医療機器メーカーや国際的な規制業務に携わるキャリアを目指す方にとって、各国・地域の規制の違いを理解することは非常に重要です。
医療機器業界について詳しく知りたい方はこちら!
「医療機器メーカーで年収1000万円もらえる?転職のコツを紹介」
「医療機器メーカーに向いている人とは?職種ごとの仕事内容も合わせて解説」
グローバルに展開する医療機器メーカーや国際的な規制業務に携わるキャリアを目指す方にとって、各国・地域の規制の違いを理解することは非常に重要です。
医療機器業界について詳しく知りたい方はこちら!
「医療機器メーカーで年収1000万円もらえる?転職のコツを紹介」
「医療機器メーカーに向いている人とは?職種ごとの仕事内容も合わせて解説」
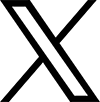
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
