医療業界で働くなら知っておきたい!バイタルとはどんなもの?
2023/12/08
2023/12/08
医療業界で働くうえで、医療現場で使われる言葉の理解は非常に重要です。MRや医療機器営業など、直接医療行為をしない仕事でも、医療従事者とのやりとりなどで触れる機会があるからです。
この記事では、診療において重要な判断材料である「バイタル」について解説します。医療業界への転職を考えている人向けにバイタルとは何か、測定方法、使用する機器などをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
この記事では、診療において重要な判断材料である「バイタル」について解説します。医療業界への転職を考えている人向けにバイタルとは何か、測定方法、使用する機器などをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
医療現場でよく聞くバイタルとはそもそもどんなもの?
バイタルは「バイタルサイン(vital signs)」を略した言葉です。日本語に訳すと、vital は「生命」、signは「兆候」で、「生命の兆候」です。つまり、人が生きている状態を示すしるしをバイタルと言います。
一般的にバイタルは、「呼吸」「体温」「血圧」「脈拍」の4つを指します。ただし、救急医療の現場や集中治療室では、意識レベルと尿量も加えた6項目を指してバイタルという場合もあります。
患者の身体の状態を数値で測ることで、正確に状況を把握し医療従事者間で伝達できます。
医療や介護の現場では「バイタルをとってください」「バイタルが安定している」といったように、バイタルという言葉が日常的に使われています。
一般的にバイタルは、「呼吸」「体温」「血圧」「脈拍」の4つを指します。ただし、救急医療の現場や集中治療室では、意識レベルと尿量も加えた6項目を指してバイタルという場合もあります。
患者の身体の状態を数値で測ることで、正確に状況を把握し医療従事者間で伝達できます。
医療や介護の現場では「バイタルをとってください」「バイタルが安定している」といったように、バイタルという言葉が日常的に使われています。
患者の命に関わる?医療現場でバイタルが重要な理由とは
バイタルを測定する目的は、患者の測定結果が正常値や基準値から外れていないか、前回の測定からどのくらい変化しているかを知ることです。
患者のバイタルが正常値・基準値から大きく外れている場合、すぐに適切に処置しなければ生命に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
また、前回測定した数値からの変化によっては、治療方針を見直さなければいけません。
バイタルは患者の生命維持や治療にとって非常に重要なものですが、【正常か】【すぐに処置が必要か】は、患者一人ひとりの状態によります。
医療従事者は、一般的な正常値・基準値を知り、患者のバイタルを定期的に測って、記録しておく必要があります。
また、容態の変化以外にも、食事・運動・入浴・排泄によってもバイタルの値は影響されます。そのため、安静な状態で毎日決まった時間で測ることが大切です。
患者のバイタルが正常値・基準値から大きく外れている場合、すぐに適切に処置しなければ生命に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
また、前回測定した数値からの変化によっては、治療方針を見直さなければいけません。
バイタルは患者の生命維持や治療にとって非常に重要なものですが、【正常か】【すぐに処置が必要か】は、患者一人ひとりの状態によります。
医療従事者は、一般的な正常値・基準値を知り、患者のバイタルを定期的に測って、記録しておく必要があります。
また、容態の変化以外にも、食事・運動・入浴・排泄によってもバイタルの値は影響されます。そのため、安静な状態で毎日決まった時間で測ることが大切です。
医療現場でバイタルはどうやって測定するの?項目ごとに解説
適切な医療を行うためにバイタルは欠かせないものです。それぞれの項目について、測定方法や必要な器具を解説します。
呼吸は、空気中の酸素を身体の中に取り入れ、二酸化炭素を排出するガス交換のことです。患者の容態が急に変わった場合、最初に呼吸を確認する必要があります。
呼吸を測定する時は、呼吸回数と呼吸の仕方をチェックします。胸やお腹の上下運動を1分間観察し「吸う・吐く」をワンセットで1回と数えます。呼吸数の正常値・基準値は、1分間あたり14~20回です。
呼吸の仕方のチェックで注意する点は、いつもの呼吸と異なる点がないかです。「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった異音がないか、苦しそうな様子ではないか、胸の動きが左右で同じかなどに気をつけましょう。呼吸音は、聴診器をあてて患者に大きく呼吸してもらって測定します。
また、患者の状態によっては「パルスオキシメーター」と呼ばれる機器を指先に着け、「動脈血酸素飽和度」を測定しなければいけません。
動脈血酸素飽和度は、血液に酸素がどれくらい供給されているかをあらわす数値です。95%を下回ると、呼吸不全の可能性があります。
日本人の平常時の体温は、36℃~36.9℃が目安です。しかし、活動量や筋肉量などによって個人差が大きく、測定する時間帯や測定前の行動の影響にも数値が左右されます。さらに朝はやや低めで、夕方になるにつれ高くなる性質があります。
患者の平熱をしっかり把握し平熱との差がどれくらいか注意する、一定の時間帯に測定するといった点が重要です。
わきの下で測定する際は、体温計を脇の真ん中に向かって斜め45度に差し込みます。体温計の先が脇の真ん中に密着するよう、患者に反対の手で体温計を挟んでいる腕をおさえてもらいます。
その他、体温計を口でくわえて測る方法や肌に直接触れずにスピーディーに測定できる「非接触体温計」を使用する方法もあるので、患者の状態などにあわせて選びましょう。
心臓から送り出された血液の流れによって血管の壁にかかる圧力を血圧といいます。血圧は、心臓が1回の動きで全身に送り出す血液の量や血管の弾力性などによって変わります。
血圧の数値を測ることで、心臓や全身の血液量の異常を早めに把握できます。特に高血圧だと、脳卒中や心筋梗塞といったさまざまな重大な病気の引き金になるので注意が必要です。
血圧計は大きくわけると、聴診器を使用しながら手動で圧力をかけるタイプと全自動タイプの2種類があります。測定時は、腕を心臓と同じ高さに置き、肘を曲げないようにして上腕または手首に巻きます。
血圧の正常値・基準値は、上が120mmHg未満、下が80mmHg未満です。ただし、血圧は測定する時間帯や姿勢などの要因によって変化しやすいため要注意です。また、病院で測る場合は患者が緊張し、高めの数値が出やすい傾向にあります。
心臓は規則的に拡大と縮小を繰り返し、血液を大動脈に送り込んでおり、その動きを「拍動(はくどう)」と言います。脈拍とは、一定の時間内に心臓が拍動する回数のことです。通常は1分間の拍動を指し、血液循環の状況を知るために重要な情報です。
脈拍は、患者にリラックスした体勢をとってもらい、人差し指・中指・薬指を揃えて、手首の親指よりも内側にある「橈骨(とうこつ)動脈」にあて、1分間測ります。
脈拍の基準値は、1分間あたり50~80回です。回数だけではなく、リズムが一定かどうかも確認するようにしましょう。
また、電動血圧計は、血圧と脈拍を同時に測定できる製品が多いので便利です。
意識レベルとは、意識障害の程度をあらわすものです。意識は「覚醒」と「認知」で構成されており、外からの刺激や呼びかけへの反応がないまたは鈍い場合は覚醒に障害がある状態。周囲の状況を正しく認識できない場合は認知に障害がある状態です。
意識障害の分類・評価方法は、「ジャパンコーマスケール(JCS)」と「グラスゴーコーマスケール(GCS)」の2種類です。
JCSは主に頭部外傷や脳血管障害の患者に使用し、GCSは外傷性脳障害による意識障害の患者に用います。
尿は、血液のろ過によって取り除かれた不要物や老廃物でできた液体です。尿は腎臓でつくられるため、腎臓機能に問題があると尿が正常に出ません。また、泌尿器の病気の場合も、尿量が極端に少なくなります。
尿量の正常値・基準値は、1回につき約200~400ml、1日合計約1,000~2,000mlです。ただし、尿量を測定するには1日に排泄される尿の量を正確に管理しなければいけません。そのため、膀胱留置カテーテルなどを使用します。
呼吸
呼吸は、空気中の酸素を身体の中に取り入れ、二酸化炭素を排出するガス交換のことです。患者の容態が急に変わった場合、最初に呼吸を確認する必要があります。
呼吸を測定する時は、呼吸回数と呼吸の仕方をチェックします。胸やお腹の上下運動を1分間観察し「吸う・吐く」をワンセットで1回と数えます。呼吸数の正常値・基準値は、1分間あたり14~20回です。
呼吸の仕方のチェックで注意する点は、いつもの呼吸と異なる点がないかです。「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった異音がないか、苦しそうな様子ではないか、胸の動きが左右で同じかなどに気をつけましょう。呼吸音は、聴診器をあてて患者に大きく呼吸してもらって測定します。
また、患者の状態によっては「パルスオキシメーター」と呼ばれる機器を指先に着け、「動脈血酸素飽和度」を測定しなければいけません。
動脈血酸素飽和度は、血液に酸素がどれくらい供給されているかをあらわす数値です。95%を下回ると、呼吸不全の可能性があります。
体温
日本人の平常時の体温は、36℃~36.9℃が目安です。しかし、活動量や筋肉量などによって個人差が大きく、測定する時間帯や測定前の行動の影響にも数値が左右されます。さらに朝はやや低めで、夕方になるにつれ高くなる性質があります。
患者の平熱をしっかり把握し平熱との差がどれくらいか注意する、一定の時間帯に測定するといった点が重要です。
わきの下で測定する際は、体温計を脇の真ん中に向かって斜め45度に差し込みます。体温計の先が脇の真ん中に密着するよう、患者に反対の手で体温計を挟んでいる腕をおさえてもらいます。
その他、体温計を口でくわえて測る方法や肌に直接触れずにスピーディーに測定できる「非接触体温計」を使用する方法もあるので、患者の状態などにあわせて選びましょう。
血圧
心臓から送り出された血液の流れによって血管の壁にかかる圧力を血圧といいます。血圧は、心臓が1回の動きで全身に送り出す血液の量や血管の弾力性などによって変わります。
血圧の数値を測ることで、心臓や全身の血液量の異常を早めに把握できます。特に高血圧だと、脳卒中や心筋梗塞といったさまざまな重大な病気の引き金になるので注意が必要です。
血圧計は大きくわけると、聴診器を使用しながら手動で圧力をかけるタイプと全自動タイプの2種類があります。測定時は、腕を心臓と同じ高さに置き、肘を曲げないようにして上腕または手首に巻きます。
血圧の正常値・基準値は、上が120mmHg未満、下が80mmHg未満です。ただし、血圧は測定する時間帯や姿勢などの要因によって変化しやすいため要注意です。また、病院で測る場合は患者が緊張し、高めの数値が出やすい傾向にあります。
脈拍
心臓は規則的に拡大と縮小を繰り返し、血液を大動脈に送り込んでおり、その動きを「拍動(はくどう)」と言います。脈拍とは、一定の時間内に心臓が拍動する回数のことです。通常は1分間の拍動を指し、血液循環の状況を知るために重要な情報です。
脈拍は、患者にリラックスした体勢をとってもらい、人差し指・中指・薬指を揃えて、手首の親指よりも内側にある「橈骨(とうこつ)動脈」にあて、1分間測ります。
脈拍の基準値は、1分間あたり50~80回です。回数だけではなく、リズムが一定かどうかも確認するようにしましょう。
また、電動血圧計は、血圧と脈拍を同時に測定できる製品が多いので便利です。
意識レベル
意識レベルとは、意識障害の程度をあらわすものです。意識は「覚醒」と「認知」で構成されており、外からの刺激や呼びかけへの反応がないまたは鈍い場合は覚醒に障害がある状態。周囲の状況を正しく認識できない場合は認知に障害がある状態です。
意識障害の分類・評価方法は、「ジャパンコーマスケール(JCS)」と「グラスゴーコーマスケール(GCS)」の2種類です。
JCSは主に頭部外傷や脳血管障害の患者に使用し、GCSは外傷性脳障害による意識障害の患者に用います。
尿量
尿は、血液のろ過によって取り除かれた不要物や老廃物でできた液体です。尿は腎臓でつくられるため、腎臓機能に問題があると尿が正常に出ません。また、泌尿器の病気の場合も、尿量が極端に少なくなります。
尿量の正常値・基準値は、1回につき約200~400ml、1日合計約1,000~2,000mlです。ただし、尿量を測定するには1日に排泄される尿の量を正確に管理しなければいけません。そのため、膀胱留置カテーテルなどを使用します。
まとめ
バイタルとは、患者の生命の状態を把握するための情報です。一般的にバイタルは、呼吸・体温・血圧・脈拍の4項目を指します。
バイタルの測定によって、患者の身体の状態が正常値・基準値から外れていないか、患者の状態がどのように変化しているかを把握できます。バイタルは、患者の生命維持や治療方針の決定に欠かせないもので、日ごろから測定・記録しなければいけません。
医療機関では、バイタルという言葉は毎日のように使われています。医療業界への転職を希望するのであれば、バイタルの基本的な知識は必須といえるでしょう。
バイタルの測定によって、患者の身体の状態が正常値・基準値から外れていないか、患者の状態がどのように変化しているかを把握できます。バイタルは、患者の生命維持や治療方針の決定に欠かせないもので、日ごろから測定・記録しなければいけません。
医療機関では、バイタルという言葉は毎日のように使われています。医療業界への転職を希望するのであれば、バイタルの基本的な知識は必須といえるでしょう。
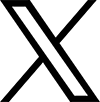
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
