MRの認定試験とは?試験概要や勉強方法を解説
2023/06/09
2025/11/11
MRになるために必要なものは一切ありませんが、製薬会社などに就職した後に取得が義務付けられているのが、MR認定試験です。MRとしての専門知識を持っていることを証明するためにあるため、MRに就職している人でMR認定試験を取得していない人はほぼいないでしょう。
しかし、試験を受ける際は受験資格を満たさなければならないので、まずは受験資格を確認して資格取得に向けた勉強をすることが大切です。
それでは、MRの認定試験についてご説明しましょう。
しかし、試験を受ける際は受験資格を満たさなければならないので、まずは受験資格を確認して資格取得に向けた勉強をすることが大切です。
それでは、MRの認定試験についてご説明しましょう。
MR認定試験とは?
MRになるために必要な資格は一切ありませんが、重要な資格となるのがMR認定試験です。
では、なぜMR認定試験が重要視されているのでしょうか。それは、ほとんどの製薬会社において、入社した後に取得が義務付けられているからです。
MR認定試験は公益財団法人のMR認定センターが開催しており、MRとして働く際に必要な専門知識が各自備わっているかどうかを確認するためにあります。つまり、試験に合格してしっかり取得している人は問題なく働けるだけの専門的な知識を持っていることが評価されるため、取得しておくに越したことはありません。
もちろんMR認定試験を取得していなくても就職できますが、就職後に取得が義務付けられている上に、病院によっては資格を取得している証拠となるMR認定証がないと入館できないこともあります。
いずれにしても、MR認定資格を取得していることで確かな専門知識を持っていることがアピールできるため、医師からの信頼を得やすいのもメリットです。
資格を取得しておけば様々な業務に対応できるようになります。よほどの理由がない限りは、就職する前でも後でほぼ確実に資格を取得することになるでしょう。
【試験の概要について】
MR認定試験は、2008年度まではMR認定センターに登録しなければなりませんでしたが、2009年度以降は、以下の条件を満たすことで誰でも受験資格が得られるようになりました。
受験資格を得るには、登録企業に在籍していない場合、MR導入教育実施期間で基礎教育を受講して修了認定を受けることです。
また、登録企業に在籍している人は、製薬企業かMR派遣業で導入教育を受講して修了認定を受けることで受験資格を得られます。
これまでの試験結果によると、全体の合格率は7割、新規受験者なら8割、再受験者なら4割と、新規受験者の方のほうが高い合格率となっております。しっかりと勉強していれば、合格できる可能性が高いため、ポイントを押さえて勉強するようにしましょう。
試験科目は医薬品情報、疾病と治療、MR総論に分かれており、全ての科目で一定以上の水準を満たすことで合格できます。なお、医師、歯科医師、薬剤師のいずれかの資格を取得している方は一部の科目が免除されるため、先にそれらの資格を取得するのも良いでしょう。
では、なぜMR認定試験が重要視されているのでしょうか。それは、ほとんどの製薬会社において、入社した後に取得が義務付けられているからです。
MR認定試験は公益財団法人のMR認定センターが開催しており、MRとして働く際に必要な専門知識が各自備わっているかどうかを確認するためにあります。つまり、試験に合格してしっかり取得している人は問題なく働けるだけの専門的な知識を持っていることが評価されるため、取得しておくに越したことはありません。
もちろんMR認定試験を取得していなくても就職できますが、就職後に取得が義務付けられている上に、病院によっては資格を取得している証拠となるMR認定証がないと入館できないこともあります。
いずれにしても、MR認定資格を取得していることで確かな専門知識を持っていることがアピールできるため、医師からの信頼を得やすいのもメリットです。
資格を取得しておけば様々な業務に対応できるようになります。よほどの理由がない限りは、就職する前でも後でほぼ確実に資格を取得することになるでしょう。
【試験の概要について】
MR認定試験は、2008年度まではMR認定センターに登録しなければなりませんでしたが、2009年度以降は、以下の条件を満たすことで誰でも受験資格が得られるようになりました。
受験資格を得るには、登録企業に在籍していない場合、MR導入教育実施期間で基礎教育を受講して修了認定を受けることです。
また、登録企業に在籍している人は、製薬企業かMR派遣業で導入教育を受講して修了認定を受けることで受験資格を得られます。
これまでの試験結果によると、全体の合格率は7割、新規受験者なら8割、再受験者なら4割と、新規受験者の方のほうが高い合格率となっております。しっかりと勉強していれば、合格できる可能性が高いため、ポイントを押さえて勉強するようにしましょう。
試験科目は医薬品情報、疾病と治療、MR総論に分かれており、全ての科目で一定以上の水準を満たすことで合格できます。なお、医師、歯科医師、薬剤師のいずれかの資格を取得している方は一部の科目が免除されるため、先にそれらの資格を取得するのも良いでしょう。
MR認定試験の勉強方法とは
MR認定試験に合格する可能性を少しでも高めるためにも、積極的に勉強するべきでしょう。
MR認定試験を勉強する際は、MRテキストと呼ばれるMR導入教育用のテキストを活用するのがおすすめです。MR認定試験は過去問を難なく解けるようなレベルであれば合格できる可能性が高いため、過去問が難なく解けるようになるまで繰り返し問題を解きましょう。
過去問題集に関しては、市販のMR認定試験の過去問題集や試験対策のための問題集が毎年最新盤の販売がされているため、勉強できる環境を整えやすいのも大きなポイントです。しかし、過去問は一度に全部解くのではなく、10問ずつ解いてから見直す方法が良いでしょう。
解いている間に分からない問題があったり、勘で解答している部分があったりしたら、その部分の問題を問題なく解けるようになるまで繰り返すことで確実に解けるようになります。またこの方法を繰り返すことで、自分の弱点が客観的に分かるようになります。自分の言葉で説明できるようになれれば、完全に覚えたといって良いでしょう。
MRとして就職する前に、自己学習にてMR認定試験を取得するのであれば、以上の勉強法がおすすめです。
1.製薬会社で行われるMR認定試験の研修
もしも製薬会社に就職してからMR認定試験の研修を受ける場合、取得に特化した研修を受けることになります。企業によって研修期間が違うものの、6ヶ月以上の研修を行う企業も存在するため、基本的にじっくりと勉強することができるでしょう。
数ヶ月も研修期間を設定しているのは、MR認定資格の受験資格の一つであるMR導入教育の条件を満たすためにあります。しっかりと研修期間を設定することで合格率が高められるため、よほどの理由がない限りは、学習環境が整った製薬会社の研修を受けるのがおすすめです。
2.もしもMR認定試験に合格できなかった場合はどうなる?
MR認定試験は研修等を受けることで合格率を高めることができますが、絶対に不合格にならないわけではありません。合格率は70%~80%程度と高いものの、それでも不合格になる可能性は十分にあります。
もしも合格できなかった場合、業務上の問題で様々な支障が出ることになります。もちろん製薬会社に就職していなければ何もデメリットはありませんが、就職していた場合は様々な制限がつくことになるでしょう。
不合格になってしまった途端にクビにされるのかと思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。不合格になってもそのまま在籍できるためクビにはなりませんが、昇格や昇給ができない可能性が高いです。製薬会社は、昇格や昇給する条件がMR認定試験の合格になっていることが多く、さらにMRにしかプロモーション許可を与えない病院は、その病院で仕事を行うことができません。
転職しようか検討している場合でも、MR経験者を募集している企業に転職しようとした際に、MR認定証を持っていることが条件になっていることが多いため、自然と希望通りの就職や転職ができなくなる可能性が高くなります。
不合格になるだけで以上のような問題が発生するため、1回で合格できるように頑張りましょう。
3.MR認定証の有効期限は5年間
無事にMR認定資格が取得できたら、次に覚えておきたいのはMR認定証の有効期限です。有効期限は5年間であり、5年ごとに更新しなければなりません。更新する時は継続教育を受けることになります。
しかし、MRの業務に就いていて企業の研修を受けていれば継続教育を受ける必要性はありません。
長く休職していたり退職したりした場合には、医療情報担当者継続センターが提供する補完教育通信講座を受講しましょう。休業や退職したからといって放置していると、資格が失効扱いになってしまうので注意が必要です。
MR認定試験を勉強する際は、MRテキストと呼ばれるMR導入教育用のテキストを活用するのがおすすめです。MR認定試験は過去問を難なく解けるようなレベルであれば合格できる可能性が高いため、過去問が難なく解けるようになるまで繰り返し問題を解きましょう。
過去問題集に関しては、市販のMR認定試験の過去問題集や試験対策のための問題集が毎年最新盤の販売がされているため、勉強できる環境を整えやすいのも大きなポイントです。しかし、過去問は一度に全部解くのではなく、10問ずつ解いてから見直す方法が良いでしょう。
解いている間に分からない問題があったり、勘で解答している部分があったりしたら、その部分の問題を問題なく解けるようになるまで繰り返すことで確実に解けるようになります。またこの方法を繰り返すことで、自分の弱点が客観的に分かるようになります。自分の言葉で説明できるようになれれば、完全に覚えたといって良いでしょう。
MRとして就職する前に、自己学習にてMR認定試験を取得するのであれば、以上の勉強法がおすすめです。
1.製薬会社で行われるMR認定試験の研修
もしも製薬会社に就職してからMR認定試験の研修を受ける場合、取得に特化した研修を受けることになります。企業によって研修期間が違うものの、6ヶ月以上の研修を行う企業も存在するため、基本的にじっくりと勉強することができるでしょう。
数ヶ月も研修期間を設定しているのは、MR認定資格の受験資格の一つであるMR導入教育の条件を満たすためにあります。しっかりと研修期間を設定することで合格率が高められるため、よほどの理由がない限りは、学習環境が整った製薬会社の研修を受けるのがおすすめです。
2.もしもMR認定試験に合格できなかった場合はどうなる?
MR認定試験は研修等を受けることで合格率を高めることができますが、絶対に不合格にならないわけではありません。合格率は70%~80%程度と高いものの、それでも不合格になる可能性は十分にあります。
もしも合格できなかった場合、業務上の問題で様々な支障が出ることになります。もちろん製薬会社に就職していなければ何もデメリットはありませんが、就職していた場合は様々な制限がつくことになるでしょう。
不合格になってしまった途端にクビにされるのかと思う方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。不合格になってもそのまま在籍できるためクビにはなりませんが、昇格や昇給ができない可能性が高いです。製薬会社は、昇格や昇給する条件がMR認定試験の合格になっていることが多く、さらにMRにしかプロモーション許可を与えない病院は、その病院で仕事を行うことができません。
転職しようか検討している場合でも、MR経験者を募集している企業に転職しようとした際に、MR認定証を持っていることが条件になっていることが多いため、自然と希望通りの就職や転職ができなくなる可能性が高くなります。
不合格になるだけで以上のような問題が発生するため、1回で合格できるように頑張りましょう。
3.MR認定証の有効期限は5年間
無事にMR認定資格が取得できたら、次に覚えておきたいのはMR認定証の有効期限です。有効期限は5年間であり、5年ごとに更新しなければなりません。更新する時は継続教育を受けることになります。
しかし、MRの業務に就いていて企業の研修を受けていれば継続教育を受ける必要性はありません。
長く休職していたり退職したりした場合には、医療情報担当者継続センターが提供する補完教育通信講座を受講しましょう。休業や退職したからといって放置していると、資格が失効扱いになってしまうので注意が必要です。
まとめ
MR認定試験は就職する前に取得しておくのがベストですが、万が一取得できなかったとしても就職した後に取得できるチャンスがあります。合格率は高めのため、しっかりと勉強していれば合格できる可能性が高いですが、もちろん不合格になる可能性があることも忘れてはいけません。
不合格になったからといってリストラされるようなことはありませんが、対応できる業務範囲が狭くなってしまうことには注意しましょう。また、合格したとしても5年ごとに更新する必要性があるため、更新期限を過ぎないようにしなければなりません。
スムーズに働けるようにするためにも、しっかりと勉強して取得しましょう。
不合格になったからといってリストラされるようなことはありませんが、対応できる業務範囲が狭くなってしまうことには注意しましょう。また、合格したとしても5年ごとに更新する必要性があるため、更新期限を過ぎないようにしなければなりません。
スムーズに働けるようにするためにも、しっかりと勉強して取得しましょう。
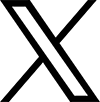
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
