MR認定試験とは?MR認定センターの取り組みと対策のポイント
2022/12/23
2025/11/11
MRとして活躍している人はもちろん、目指している人も「MR認定センター」という名前を耳にしたことがあるかと思います。
MR認定センターは、MRにとって重要な団体です。しかし、名前は聞いていても詳しい役割などを知らない人も多いでしょう。この記事では、MR認定センターの概要やMR認定試験対策など、詳しく解説します。
MR認定センターは、MRにとって重要な団体です。しかし、名前は聞いていても詳しい役割などを知らない人も多いでしょう。この記事では、MR認定センターの概要やMR認定試験対策など、詳しく解説します。
MR認定センターって何をしているの?主な役割や取り組みを紹介
MRは、製薬会社やMR専門のアウトソーシング会社(CSO)に所属し、医師などの医療従事者への医薬品情報提供を通し、担当する医薬品の導入につなげる職業です。
MRの主な業務は、下記の3つです。
・医薬品が正しく使われ普及するのを手助けする
・医療現場から医薬品の効き目などの有効性情報や副作用などの安全性情報を収集し、製薬会社や厚生労働省などに報告する
・医療現場から集めた情報を正しく医療従事者に伝える
優れた医薬品が多くの人に正しく使われるように活動し、人々の命や健康を守るのがMRの使命といえます。
MR認定センターは、医薬品が正しく使われるためには医薬品情報のスペシャリストであるMRが必要不可欠だと考え、MRの質の向上を目指した活動をしています。
活動の目標は、MRが深い知見・誇り・やりがいを持って仕事に取り組めるようにするとともに、医療従事者にとって信頼できるパートナーとなり、人々の保健衛生の向上に貢献することです。
活動内容は、MRとして必要な知識・スキルを習得できているかを客観的に評価する「MR認定試験」、「MR学習ポータル」をはじめとする教育研修、広報や啓発活動、企画・調査研修など多岐にわたります。
MRの主な業務は、下記の3つです。
・医薬品が正しく使われ普及するのを手助けする
・医療現場から医薬品の効き目などの有効性情報や副作用などの安全性情報を収集し、製薬会社や厚生労働省などに報告する
・医療現場から集めた情報を正しく医療従事者に伝える
優れた医薬品が多くの人に正しく使われるように活動し、人々の命や健康を守るのがMRの使命といえます。
MR認定センターは、医薬品が正しく使われるためには医薬品情報のスペシャリストであるMRが必要不可欠だと考え、MRの質の向上を目指した活動をしています。
活動の目標は、MRが深い知見・誇り・やりがいを持って仕事に取り組めるようにするとともに、医療従事者にとって信頼できるパートナーとなり、人々の保健衛生の向上に貢献することです。
活動内容は、MRとして必要な知識・スキルを習得できているかを客観的に評価する「MR認定試験」、「MR学習ポータル」をはじめとする教育研修、広報や啓発活動、企画・調査研修など多岐にわたります。
MR認定試験の概要とは?試験対策はどうするの?
MR認定センターの事業のなかでも、MR認定試験はMR業務と深く関係する重要なものです。ここでは、MR認定試験の概要や試験対策などを詳しく解説します。
MR認定試験とは、MRにとって必要な資質を身につける「MR導入教育」の成果を評価するための試験です。毎年12月に実施されており、合格者は6ヶ月のMR経験を終了後に発行申請することで「MR認定証」を取得できます。
スキル向上のために、5年ごとの更新が定められており、所定の認定研修と更新時確認ドリルの修了が必須です。
MR資格の有効期限が切れるタイミングで、製薬会社に勤務していないなどの理由で更新をせず、失効するケースもあります。その場合は、再度認定試験を受け、資格を取り直さなければいけません。
MRは、医師や看護師などとは異なり、業務に携わるために必須の資格はありません。しかし、製薬会社やCSOの多くは、MR認定証の取得を義務づけています。ほとんどの場合、入社1年目の12月頃にMR試験を受験します。
MR認定資格の受験資格は、下記の通りです。
・MR認定センター登録企業(製薬会社またはCSO)に在籍中
在籍している企業で導入教育を受け、修了認定済み
・MR認定センター登録企業に在籍していない
MR導入教育実施機関で300時間にわたる基礎教育を受講し、修了認定済み
MRとして就職する場合、ほとんどの企業で未経験者は入社後に研修を受けられるため、応募の時点で試験に合格していなくても問題はありません。
MR試験の試験科目は、「医薬品情報」「疾病と治療」「MR総論」の3科目です。問題形式は選択式で、5つの選択肢のうち1つを選びます。問題数は、医薬品情報が80問・疾病と治療が110問・MR総論が80問で、配点は1問1点です。
医師・歯科医師・薬剤師いずれかの資格を取得していれば、医薬品情報・疾病と治療の2科目が免除されます。
試験問題は、MR認定センター発行の「MRテキスト」の内容に沿って出題されます。全ての科目で、一定以上の水準をクリアすると合格です。具体的な点数は公表されていませんが、例年は7~8割の正答率が合格ラインです。試験結果は、申請時に入力した住所に送られます。
2021年12月に開催されたMR認定試験の合格率は、全体で79.4%、新規受験者のみでは83.3%、再受験者は60.5%です。これまでの試験結果の傾向として、全体の合格率は70%程度、新規受験者のみの数値は80%程度、再受験者は40%程度です。
MR認定試験は、覚える内容が多く医学系の知識が必要なので、簡単ではありません。しかし、全体の合格率は約80%と高く、大手製薬会社やCSOでは90%以上のMRが合格するといわれています。しっかり取り組めば、合格しやすい試験だといえるでしょう。
2023年12月10日に実施された第30回MR認定試験要項をもとに、MR認定試験の申し込み方法などについて解説します。申し込み方法などは変更になる可能性があるので、必ずMR認定センターのHPで最新の情報を確認しましょう。
MR認定試験の受験申し込みは、 MR学習ポータル から行います。無料でアカウントを作成し、マイページの各種申請内にある「MR 認定試験受験申請」の申請ボタンを押して、必要事項を入力します。
申し込み期限は毎年9月末日前後で、第30回MR認定試験の受験申請締切日は、2023年9月30日でした。科目免除対象者の資格証明送付期限は、受験申請締切日よりも前なので注意しましょう。
受験料は、2科目以上受験する場合は 13,200 円(税込)、1科目受験する場合は 8,800 円(税込)です。受験料の支払期限は、受験申請締切日までです。
試験地は、東京・大阪の2か所で、大学の構内で実施するのが一般的です。受験申請締切日を過ぎると、試験地の変更はできません。
MR認定試験は、MR導入教育用につくられたMRテキストの内容から出題されます。合格するためには、テキストの内容を理解し、過去問を繰り返し解くことが大切です。
また、合格ラインは正答率7~8割程度で、全科目で合格する必要があります。苦手科目・分野をつくらないよう、まんべんなく学ぶことが大切です。
まずは、MRセンター登録企業で実施される導入教育やMR導入教育実施機関で行われる基礎教育の内容をしっかり理解し、知識を身につけましょう。勤務先によっては、6ヶ月以上の研修期間を設け、集中的に試験対策を実施するケースもあります。
自分でスケジュールを決めて勉強する場合は、遅くとも試験の3ヶ月くらい前には勉強スタートするのをおすすめします。
また、講義以外にも、テキストによる復習や、過去問演習によるアウトプットの練習といった勉強は必須です。理解できていないポイントは、何度も見直しや問題演習をすると効果的です。eラーニングや模擬試験などを活用すれば、より効率的に勉強できるでしょう。
過去問や対策用の問題集を説いた後は、不正解の問題やカンで正解した問題をチェックし、理解を深めます。問題に登場した単語を自分の言葉で説明できるようになるまで、理解を深めましょう。
試験直前の1週間は、過去問の演習や苦手な部分の復習にあてると、点数アップにつながります。
MR導入用につくられたテキストや過去問集、試験対策用の問題集は、基本的に毎年最新版が発売されています。医学は日々進歩していますし、医薬品に関する法律やルールは日々変化しています。過去の教材を持っていたとしても、最新版で勉強するようにしましょう。
(1)MR認定試験とは
MR認定試験とは、MRにとって必要な資質を身につける「MR導入教育」の成果を評価するための試験です。毎年12月に実施されており、合格者は6ヶ月のMR経験を終了後に発行申請することで「MR認定証」を取得できます。
スキル向上のために、5年ごとの更新が定められており、所定の認定研修と更新時確認ドリルの修了が必須です。
MR資格の有効期限が切れるタイミングで、製薬会社に勤務していないなどの理由で更新をせず、失効するケースもあります。その場合は、再度認定試験を受け、資格を取り直さなければいけません。
MRは、医師や看護師などとは異なり、業務に携わるために必須の資格はありません。しかし、製薬会社やCSOの多くは、MR認定証の取得を義務づけています。ほとんどの場合、入社1年目の12月頃にMR試験を受験します。
MR認定資格の受験資格は、下記の通りです。
・MR認定センター登録企業(製薬会社またはCSO)に在籍中
在籍している企業で導入教育を受け、修了認定済み
・MR認定センター登録企業に在籍していない
MR導入教育実施機関で300時間にわたる基礎教育を受講し、修了認定済み
MRとして就職する場合、ほとんどの企業で未経験者は入社後に研修を受けられるため、応募の時点で試験に合格していなくても問題はありません。
(2)MR試験の試験科目・難易度
MR試験の試験科目は、「医薬品情報」「疾病と治療」「MR総論」の3科目です。問題形式は選択式で、5つの選択肢のうち1つを選びます。問題数は、医薬品情報が80問・疾病と治療が110問・MR総論が80問で、配点は1問1点です。
医師・歯科医師・薬剤師いずれかの資格を取得していれば、医薬品情報・疾病と治療の2科目が免除されます。
試験問題は、MR認定センター発行の「MRテキスト」の内容に沿って出題されます。全ての科目で、一定以上の水準をクリアすると合格です。具体的な点数は公表されていませんが、例年は7~8割の正答率が合格ラインです。試験結果は、申請時に入力した住所に送られます。
2021年12月に開催されたMR認定試験の合格率は、全体で79.4%、新規受験者のみでは83.3%、再受験者は60.5%です。これまでの試験結果の傾向として、全体の合格率は70%程度、新規受験者のみの数値は80%程度、再受験者は40%程度です。
MR認定試験は、覚える内容が多く医学系の知識が必要なので、簡単ではありません。しかし、全体の合格率は約80%と高く、大手製薬会社やCSOでは90%以上のMRが合格するといわれています。しっかり取り組めば、合格しやすい試験だといえるでしょう。
(3)MR認定試験の申し込み方法
2023年12月10日に実施された第30回MR認定試験要項をもとに、MR認定試験の申し込み方法などについて解説します。申し込み方法などは変更になる可能性があるので、必ずMR認定センターのHPで最新の情報を確認しましょう。
MR認定試験の受験申し込みは、 MR学習ポータル から行います。無料でアカウントを作成し、マイページの各種申請内にある「MR 認定試験受験申請」の申請ボタンを押して、必要事項を入力します。
申し込み期限は毎年9月末日前後で、第30回MR認定試験の受験申請締切日は、2023年9月30日でした。科目免除対象者の資格証明送付期限は、受験申請締切日よりも前なので注意しましょう。
受験料は、2科目以上受験する場合は 13,200 円(税込)、1科目受験する場合は 8,800 円(税込)です。受験料の支払期限は、受験申請締切日までです。
試験地は、東京・大阪の2か所で、大学の構内で実施するのが一般的です。受験申請締切日を過ぎると、試験地の変更はできません。
(4)MR認定試験の対策
MR認定試験は、MR導入教育用につくられたMRテキストの内容から出題されます。合格するためには、テキストの内容を理解し、過去問を繰り返し解くことが大切です。
また、合格ラインは正答率7~8割程度で、全科目で合格する必要があります。苦手科目・分野をつくらないよう、まんべんなく学ぶことが大切です。
まずは、MRセンター登録企業で実施される導入教育やMR導入教育実施機関で行われる基礎教育の内容をしっかり理解し、知識を身につけましょう。勤務先によっては、6ヶ月以上の研修期間を設け、集中的に試験対策を実施するケースもあります。
自分でスケジュールを決めて勉強する場合は、遅くとも試験の3ヶ月くらい前には勉強スタートするのをおすすめします。
また、講義以外にも、テキストによる復習や、過去問演習によるアウトプットの練習といった勉強は必須です。理解できていないポイントは、何度も見直しや問題演習をすると効果的です。eラーニングや模擬試験などを活用すれば、より効率的に勉強できるでしょう。
過去問や対策用の問題集を説いた後は、不正解の問題やカンで正解した問題をチェックし、理解を深めます。問題に登場した単語を自分の言葉で説明できるようになるまで、理解を深めましょう。
試験直前の1週間は、過去問の演習や苦手な部分の復習にあてると、点数アップにつながります。
MR導入用につくられたテキストや過去問集、試験対策用の問題集は、基本的に毎年最新版が発売されています。医学は日々進歩していますし、医薬品に関する法律やルールは日々変化しています。過去の教材を持っていたとしても、最新版で勉強するようにしましょう。
万が一MR認定試験に落ちるとどうなるの?主な影響を紹介
MR認定試験に合格できなかった場合、どのような悪影響が生じるのかを紹介します。
まれではありますが、MR認定資格を取得していないMRの訪問を受け付けていない医療機関もあります。数は多くないものの、MRとしての活動の幅が狭まってしまいます。
また、MR認定試験で問われる知識は、仕事をするうえで不可欠なものばかりです。正しい知識にもとづいて業務に取り組むためにも、しっかり試験勉強しましょう。
製薬会社でMRとして働くには、基本的にはMR認定資格が必須です。そのため不合格だと、社内評価・ボーナス・昇給などにも影響します。外資系の製薬会社の場合は、2年連続で不合格の場合は解雇されてしまう場合があるほどです。
大きな影響がなくても、他のMRの多くが試験に受かっていると考えると、肩身の狭い思いをするかもしれません。
勤務先によっては、2年目に認定試験を受ける場合のサポートはあまりない可能性があります。また、営業活動など実務が忙しくなり、十分に試験勉強の時間を取れないかもしれません。
「2年目に受かればいい」と思っていると、次の試験でも不合格になりかねないので要注意です。
新薬メーカーのMR求人の多くは、MR認定資格が必須条件になっている場合が少なくありません。MR認定資格がないことで、転職時の選択肢が狭まる可能性があります。
また、MRとしての勤務実績があるにもかかわらずMR認定資格を習得していないと、採用担当者に知識・スキルを疑問視されるかもしれません。
(1)活動できない医療機関がある
まれではありますが、MR認定資格を取得していないMRの訪問を受け付けていない医療機関もあります。数は多くないものの、MRとしての活動の幅が狭まってしまいます。
また、MR認定試験で問われる知識は、仕事をするうえで不可欠なものばかりです。正しい知識にもとづいて業務に取り組むためにも、しっかり試験勉強しましょう。
(2)社内評価に関わる
製薬会社でMRとして働くには、基本的にはMR認定資格が必須です。そのため不合格だと、社内評価・ボーナス・昇給などにも影響します。外資系の製薬会社の場合は、2年連続で不合格の場合は解雇されてしまう場合があるほどです。
大きな影響がなくても、他のMRの多くが試験に受かっていると考えると、肩身の狭い思いをするかもしれません。
(3)受験に向けたサポートがなくなる
勤務先によっては、2年目に認定試験を受ける場合のサポートはあまりない可能性があります。また、営業活動など実務が忙しくなり、十分に試験勉強の時間を取れないかもしれません。
「2年目に受かればいい」と思っていると、次の試験でも不合格になりかねないので要注意です。
(4)MRへの転職に影響する
新薬メーカーのMR求人の多くは、MR認定資格が必須条件になっている場合が少なくありません。MR認定資格がないことで、転職時の選択肢が狭まる可能性があります。
また、MRとしての勤務実績があるにもかかわらずMR認定資格を習得していないと、採用担当者に知識・スキルを疑問視されるかもしれません。
MR認定試験は今後どう変わるの?MR認定センター局長のビジョンとは
医薬品を取り巻く状況の変化に伴い、MRの役割やMR認定試験のあり方も変化します。2022年2月にMR認定センターの近澤洋平事務局長が明らかにした、認定試験制度改革方針を2点紹介します。
MR認定試験の受験者の多くは、MRとして働いている人です。MR認定センターは、MRの受験資格を緩和することで、MRを志望する薬学部の学生などにも働きかけ、MR志願者増につなげたいと考えています。
また、受験資格の緩和により、製薬会社やCSOが実施している基礎教育の負担を軽減し、実務教育に力を入れられるようサポートする意向です。
近澤事務局長は、技能士資格MR認定を仕事に必要な技能の習得レベルを評価する「技能士資格」として行う構想について説明しました。例えば、3級合格者はMRの入り口部分の基礎教育を修了していると評価し、2級では客観的に実務教育を評価するといった運用です。
また、別案として認定方式を2段階方式にし、1段階目では、GVP省令に基づく医薬情報担当者として、基礎教育レベルをクリアしていると認定。合格者が製薬会社などでの実務経験を経て、2段階目にあたるMR認定試験を受験するというものです。
2段階方式にすることで、薬学部の学生などに受験資格を拡大できる、試験実施時期の融通が利くようになり企業の負担を軽減できるといったメリットが期待できます。
MR認定資格制度の改革が進めば、受験資格や試験対策、更新制度なども変更されるかもしれません。これからMR認定資格を取る人はもちろん、すでに取得している人も、動向をチェックしましょう。
(1)受験資格の緩和
MR認定試験の受験者の多くは、MRとして働いている人です。MR認定センターは、MRの受験資格を緩和することで、MRを志望する薬学部の学生などにも働きかけ、MR志願者増につなげたいと考えています。
また、受験資格の緩和により、製薬会社やCSOが実施している基礎教育の負担を軽減し、実務教育に力を入れられるようサポートする意向です。
(2)認定試験の仕組みの変更
近澤事務局長は、技能士資格MR認定を仕事に必要な技能の習得レベルを評価する「技能士資格」として行う構想について説明しました。例えば、3級合格者はMRの入り口部分の基礎教育を修了していると評価し、2級では客観的に実務教育を評価するといった運用です。
また、別案として認定方式を2段階方式にし、1段階目では、GVP省令に基づく医薬情報担当者として、基礎教育レベルをクリアしていると認定。合格者が製薬会社などでの実務経験を経て、2段階目にあたるMR認定試験を受験するというものです。
2段階方式にすることで、薬学部の学生などに受験資格を拡大できる、試験実施時期の融通が利くようになり企業の負担を軽減できるといったメリットが期待できます。
MR認定資格制度の改革が進めば、受験資格や試験対策、更新制度なども変更されるかもしれません。これからMR認定資格を取る人はもちろん、すでに取得している人も、動向をチェックしましょう。
MR認定試験合格後のキャリアパスって?代表的な4つについて解説
MRのキャリアにおいて、MR認定試験はスタートに過ぎません。その後のキャリアパスについて代表的な4つを紹介します。
一つの職場でMRとして成果を出し、営業所長クラス・エリアマネージャー・支店長クラスと高いポジションを目指すキャリアパスです。管理職ともなると、満足できる年収を得られる可能性が高いでしょう。特にインセンティブの割合が多い外資系製薬メーカーに勤務している場合は、かなりの高年収を期待できます。
管理職になるには、知識・人脈・成果を活かして、社内評価を上げなければいけません。自分が成果を出すだけではなく、チームでの目標達成や部下の育成といったマネジメント能力が求められます。
また、自社内でキャリアアップするだけではなく、より高いポジションと年収を提示する他の企業に転職するのも方法のひとつです。
希少疾患領域・遺伝子治療・生物学的製剤・再生医療など、将来的にも成長が見込まれる、ニーズの高い領域に挑戦するのも方法のひとつです。
・希少疾患領域
オンコロジー(がん)・中枢神経系・免疫系疾患などを指します。
・遺伝子治療
遺伝子を編集することで、遺伝子疾患を根本的に治療する方法です。
・生物学的製剤
遺伝子組み換え技術などのバイオテクノロジーを用いてつくる薬剤です。
・再生医療
幹細胞を培養養殖して体内に移植するなどの方法で、臓器や組織の機能などを回復する治療です。
大手製薬会社はもちろん、新規参入のベンチャー企業も多く、求人が活発です。今後の医薬品は、上記の領域をはじめとする患者それぞれに合わせた治療が主流になっていくと考えられます。今のうちから経験を積んでおくことで、将来のキャリアが非常に有利になるはずです。
ただし、MRから人気のある領域のため、競争率が高く、転職するのは簡単ではありません。上記の領域に近い領域の経験、大学病院や高度で専門的な医療を提供する基幹病院での経験などが問われます。特に大手製薬会社は狭き門です。
CSOであれば担当領域の希望が通りやすいので、まずはCSOに転職してその領域の経験を積むといったキャリアプランがおすすめです。専門スキルを磨くことで、大手製薬会社をはじめとするさらに条件の良い職場への転職も視野に入れられます。
MR業務によって培った医薬品の知見を活かして、製薬業界の他の職種にチャレンジするキャリアパスもあります。
別の職種に挑戦する場合は、在籍する企業の社内公募に手を挙げるルートがスムーズです。MRから挑戦しやすい職種としては、MRやリーダーを育成するトレーナーやマーケティング、「MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)」などがあります。
MSLとは、高度な医学・薬学・科学的知識をもとに、最新の医学情報を医師などの医療従事者に提供する職種です。臨床研究や論文投稿のサポートも重要な役割です。
MRが情報を提供することで処方をプロモーションすることを目的に仕事をするのに対し、MSLは製薬会社と医療現場の中立的な立場から発信し自社や自社製品の価値を高めることが目的です。
MSLは、日本ではまだあまり知られていませんが、欧米では50年以上前に確立された職業です。患者中心の医療を目指す動きが進むなか、日本でも外資系企業を中心に採用が行われています。
今後ますますニーズが高まると考えられるため、今のうちからキャリアを積んでおくのもおすすめです。
自社以外の製薬会社に転職して他の職種にチャレンジする方法もありますが、多くの場合は即戦力が求められるため、書類選考に通らないケースも少なくありません。採用されたとしても、年収が下がる可能性が高いので、どんなキャリアを歩みたいか良く考えて決断しましょう。
MRとして培った営業力と医療の知識、医療現場への理解を活かして、製薬業界以外で活躍する道もあります。
医療機器営業や医療業界専門のコンサルタント・人材紹介・広告代理店・マーケティング会社・IT企業など、MR経験のある人材を求めている企業は少なくありません。製薬業界だけでなく、医療業界全体に目を向けることで、より良いキャリアを歩める可能性があります。
(1)管理職としてステップアップする
一つの職場でMRとして成果を出し、営業所長クラス・エリアマネージャー・支店長クラスと高いポジションを目指すキャリアパスです。管理職ともなると、満足できる年収を得られる可能性が高いでしょう。特にインセンティブの割合が多い外資系製薬メーカーに勤務している場合は、かなりの高年収を期待できます。
管理職になるには、知識・人脈・成果を活かして、社内評価を上げなければいけません。自分が成果を出すだけではなく、チームでの目標達成や部下の育成といったマネジメント能力が求められます。
また、自社内でキャリアアップするだけではなく、より高いポジションと年収を提示する他の企業に転職するのも方法のひとつです。
(2)ニーズの高い領域に挑戦する
希少疾患領域・遺伝子治療・生物学的製剤・再生医療など、将来的にも成長が見込まれる、ニーズの高い領域に挑戦するのも方法のひとつです。
・希少疾患領域
オンコロジー(がん)・中枢神経系・免疫系疾患などを指します。
・遺伝子治療
遺伝子を編集することで、遺伝子疾患を根本的に治療する方法です。
・生物学的製剤
遺伝子組み換え技術などのバイオテクノロジーを用いてつくる薬剤です。
・再生医療
幹細胞を培養養殖して体内に移植するなどの方法で、臓器や組織の機能などを回復する治療です。
大手製薬会社はもちろん、新規参入のベンチャー企業も多く、求人が活発です。今後の医薬品は、上記の領域をはじめとする患者それぞれに合わせた治療が主流になっていくと考えられます。今のうちから経験を積んでおくことで、将来のキャリアが非常に有利になるはずです。
ただし、MRから人気のある領域のため、競争率が高く、転職するのは簡単ではありません。上記の領域に近い領域の経験、大学病院や高度で専門的な医療を提供する基幹病院での経験などが問われます。特に大手製薬会社は狭き門です。
CSOであれば担当領域の希望が通りやすいので、まずはCSOに転職してその領域の経験を積むといったキャリアプランがおすすめです。専門スキルを磨くことで、大手製薬会社をはじめとするさらに条件の良い職場への転職も視野に入れられます。
(3)製薬業界内でキャリアチェンジする
MR業務によって培った医薬品の知見を活かして、製薬業界の他の職種にチャレンジするキャリアパスもあります。
別の職種に挑戦する場合は、在籍する企業の社内公募に手を挙げるルートがスムーズです。MRから挑戦しやすい職種としては、MRやリーダーを育成するトレーナーやマーケティング、「MSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)」などがあります。
MSLとは、高度な医学・薬学・科学的知識をもとに、最新の医学情報を医師などの医療従事者に提供する職種です。臨床研究や論文投稿のサポートも重要な役割です。
MRが情報を提供することで処方をプロモーションすることを目的に仕事をするのに対し、MSLは製薬会社と医療現場の中立的な立場から発信し自社や自社製品の価値を高めることが目的です。
MSLは、日本ではまだあまり知られていませんが、欧米では50年以上前に確立された職業です。患者中心の医療を目指す動きが進むなか、日本でも外資系企業を中心に採用が行われています。
今後ますますニーズが高まると考えられるため、今のうちからキャリアを積んでおくのもおすすめです。
自社以外の製薬会社に転職して他の職種にチャレンジする方法もありますが、多くの場合は即戦力が求められるため、書類選考に通らないケースも少なくありません。採用されたとしても、年収が下がる可能性が高いので、どんなキャリアを歩みたいか良く考えて決断しましょう。
(4)製薬業界以外の仕事にキャリアチェンジする
MRとして培った営業力と医療の知識、医療現場への理解を活かして、製薬業界以外で活躍する道もあります。
医療機器営業や医療業界専門のコンサルタント・人材紹介・広告代理店・マーケティング会社・IT企業など、MR経験のある人材を求めている企業は少なくありません。製薬業界だけでなく、医療業界全体に目を向けることで、より良いキャリアを歩める可能性があります。
まとめ
MR認定センターは、MRの質を向上するための活動をしています。医療従事者から信頼されるパートナーとして医薬品の適正な使用を促進し、多くの人の保健衛生を向上させるという目標を掲げています。
MR認定センターの主な事業は、MRとして必要な知識・スキルの有無を評価するMR認定試験の運営、教育研修などです。
MR認定資格がなくても、MR業務に携われますが、多くの企業では取得を必須としています。合格率は8割前後なので、MRテキストや過去問を使い、真剣に取り組めば合格しやすいといえるでしょう。
今後は、受験資格を緩める、MR認定資格を2段階方式にするなどの改革が行われる可能性があります。これからMR認定試験を受ける人はもちろん、すでに取得している人にも影響が出るかもしれません。MR認定センターのホームページや医療業界に特化した専門サイトなどで、情報をチェックしましょう。
MR認定試験合格後のキャリアパスとしては、管理職としてステップアップする・ニーズの高い領域に挑戦する・製薬業界内でキャリアチェンジする・製薬業界以外の仕事にキャリアチェンジするなどがあります。
MR認定センターの主な事業は、MRとして必要な知識・スキルの有無を評価するMR認定試験の運営、教育研修などです。
MR認定資格がなくても、MR業務に携われますが、多くの企業では取得を必須としています。合格率は8割前後なので、MRテキストや過去問を使い、真剣に取り組めば合格しやすいといえるでしょう。
今後は、受験資格を緩める、MR認定資格を2段階方式にするなどの改革が行われる可能性があります。これからMR認定試験を受ける人はもちろん、すでに取得している人にも影響が出るかもしれません。MR認定センターのホームページや医療業界に特化した専門サイトなどで、情報をチェックしましょう。
MR認定試験合格後のキャリアパスとしては、管理職としてステップアップする・ニーズの高い領域に挑戦する・製薬業界内でキャリアチェンジする・製薬業界以外の仕事にキャリアチェンジするなどがあります。
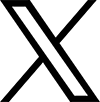
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
