言語聴覚士とはどんな職種?仕事内容や目指し方などを解説
2022/12/09
2022/12/09
言語聴覚士は、ことばによるコミュニケーションの障害やものを飲み込む能力の障害を持つ人をサポートするスペシャリストです。
比較的新しい職業ですが、高齢化などを背景にニーズが高まりつつあります。この記事では、言語聴覚士の概要や仕事内容などを詳しく解説します。
比較的新しい職業ですが、高齢化などを背景にニーズが高まりつつあります。この記事では、言語聴覚士の概要や仕事内容などを詳しく解説します。
言語聴覚士とはどんな職業?どんな就職先があるの?詳しく解説
言語聴覚士の概要や主な勤務先を解説します。
(1)言語聴覚士とは
言語聴覚士は英語で「Speech Therapist」と呼ばれており、頭文字をとって「ST」と略されます。名前の通り、ことばを使ったコミュニケーションの障害を持つ人に対しリハビリテーションなどのサポートをする職種です。また、ものを飲み込む機能に障害が出る「嚥下障害(えんげしょうがい)」をはじめとする口腔に関する問題を持つ人の支援も行います。
リハビリテーションというとケガや病気で失った手足の機能の回復というイメージがあるかもしれません。しかし、言語聴覚士の専門領域である、ことばを使ったコミュニケーションや食べたり飲んだりすることは、生きていくうえで非常に大切なことです。
日本言語聴覚士協会の会員数は、2022年4月1日現在で19,789人。そのうち女性が15,052人と約76%を占めます。
(2)言語聴覚士の主な就職先
言語聴覚士が多く活躍する職場は、以下の通りです。
・医療機関
言語聴覚士の約7割が医療機関で働いています。主な勤務先は、病院のリハビリテーション科やリハビリテーションセンター、回復期病棟での勤務です。その他、口腔外科や耳鼻咽喉科で働く人もいます。患者一人ひとりの障害や状態に合わせて、リハビリテーションや指導を実施し、社会復帰を目指します。
また、声に関する悩みをサポートする音声外科など、専門性の高いクリニックで活躍するケースもあります。
・介護&福祉施設
特別養護老人ホームをはじめとする高齢者向け施設や訪問リハビリテーションに勤務し、介護スタッフや栄養士と協力して、摂食嚥下障害のリハビリテーションを実施します。また、ある言語・認知機能の維持回復を目的としたレクリエーションも重要な仕事です。
肢体不自由児施設など子どもを対象とする施設では、聴覚障害・摂食嚥下障害・言語障害のある子どもに対し、訓練や指導を実施します。また、家族の相談に乗りアドバイスをします。
2006年に言語聴覚士による訪問リハビリテーションに介護保険が適用されるようになるなど、年々ニーズが高まっています。
・教育機関
特別支援学校などで教員として子どもたちの支援をする、言語聴覚士養成校の講師として学生を指導するといった道もあります。ただし、特別支援学校などで教員になるには、言語聴覚士資格だけではなく、教員免許も必要です。
(1)言語聴覚士とは
言語聴覚士は英語で「Speech Therapist」と呼ばれており、頭文字をとって「ST」と略されます。名前の通り、ことばを使ったコミュニケーションの障害を持つ人に対しリハビリテーションなどのサポートをする職種です。また、ものを飲み込む機能に障害が出る「嚥下障害(えんげしょうがい)」をはじめとする口腔に関する問題を持つ人の支援も行います。
リハビリテーションというとケガや病気で失った手足の機能の回復というイメージがあるかもしれません。しかし、言語聴覚士の専門領域である、ことばを使ったコミュニケーションや食べたり飲んだりすることは、生きていくうえで非常に大切なことです。
日本言語聴覚士協会の会員数は、2022年4月1日現在で19,789人。そのうち女性が15,052人と約76%を占めます。
(2)言語聴覚士の主な就職先
言語聴覚士が多く活躍する職場は、以下の通りです。
・医療機関
言語聴覚士の約7割が医療機関で働いています。主な勤務先は、病院のリハビリテーション科やリハビリテーションセンター、回復期病棟での勤務です。その他、口腔外科や耳鼻咽喉科で働く人もいます。患者一人ひとりの障害や状態に合わせて、リハビリテーションや指導を実施し、社会復帰を目指します。
また、声に関する悩みをサポートする音声外科など、専門性の高いクリニックで活躍するケースもあります。
・介護&福祉施設
特別養護老人ホームをはじめとする高齢者向け施設や訪問リハビリテーションに勤務し、介護スタッフや栄養士と協力して、摂食嚥下障害のリハビリテーションを実施します。また、ある言語・認知機能の維持回復を目的としたレクリエーションも重要な仕事です。
肢体不自由児施設など子どもを対象とする施設では、聴覚障害・摂食嚥下障害・言語障害のある子どもに対し、訓練や指導を実施します。また、家族の相談に乗りアドバイスをします。
2006年に言語聴覚士による訪問リハビリテーションに介護保険が適用されるようになるなど、年々ニーズが高まっています。
・教育機関
特別支援学校などで教員として子どもたちの支援をする、言語聴覚士養成校の講師として学生を指導するといった道もあります。ただし、特別支援学校などで教員になるには、言語聴覚士資格だけではなく、教員免許も必要です。
幅広い障害を持つ人をサポート!言語聴覚士の仕事内容とは
言語聴覚士の仕事内容は、患者の障害や状況に合わせて異なります。代表的な障害別に仕事内容を紹介します。
(1)聴覚障害
周りの音や声が聞こえないまたは聞き取りにくい「難聴」など、聴覚に関係する障害を持つ人をサポートします。聴覚検査により障害の程度や種類などを把握し、補聴器の調整や人工内耳設置後のリハビリテーションをします。
(2)言語・コミュニケーションの障害
「失語症」「構音障害」などの言語・コミュニケーションの障害がある人を対象に、リハビリテーションを実施します。検査や評価を通して障害の状態・原因・経過などを把握し、言葉の理解・発話・読み書きの訓練やアドバイスをして、社会復帰へとつなげます。
(3)子どもの言語発達・コミュニケーション障害
発達障害・聴覚障害・知的障害があると、親や周囲の人との会話や周りからの声かけによって自然に語彙や文法などを習得することが難しい場合もあります。
言語発達を促すため、周囲の人たちのコミュニケーションに関心が持てるようサポートする、語彙や文法を身につける訓練をする、家族や学校と連携して環境を整えるなどの支援をします。
(4)摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)
「摂食嚥下」とは食べて飲み込むことです。加齢や障害などが原因で、食べ物をスムーズに飲み込めない患者に対し、食事機能を維持するサポートをします。
摂食嚥下障害は特に高齢者に多く、歯の喪失・舌やあごの筋肉の衰え・脳卒中による麻痺などさまざまな原因が考えられます。
摂食嚥下障害を放置すると、栄養状態の悪化だけでなく、飲食物が誤って気管に入る「誤嚥(ごえん)」を引き起こしかねません。誤嚥によって肺炎になると、亡くなってしまう場合もあるため、摂食嚥下障害の対応は非常に大切です。
また、摂食嚥下障害が重度になると胃瘻となり、チューブによって栄養を摂取せざるを得なくなる場合があります。
言語聴覚士は、食事機能の維持・回復をサポートするとともに、その患者が摂食嚥下できる食事などのアドバイスもします。
(5)認知機能の障害
知覚・記憶・思考・感情など社会生活を送るうえで必要な機能を「認知機能」と呼びます。認知機能が低下する原因として代表的なのが、高次機能障害や認知症です。
言語聴覚士は、認知障害の評価やリハビリテーションを通して、社会生活を送れるようサポートします。
(1)聴覚障害
周りの音や声が聞こえないまたは聞き取りにくい「難聴」など、聴覚に関係する障害を持つ人をサポートします。聴覚検査により障害の程度や種類などを把握し、補聴器の調整や人工内耳設置後のリハビリテーションをします。
(2)言語・コミュニケーションの障害
「失語症」「構音障害」などの言語・コミュニケーションの障害がある人を対象に、リハビリテーションを実施します。検査や評価を通して障害の状態・原因・経過などを把握し、言葉の理解・発話・読み書きの訓練やアドバイスをして、社会復帰へとつなげます。
(3)子どもの言語発達・コミュニケーション障害
発達障害・聴覚障害・知的障害があると、親や周囲の人との会話や周りからの声かけによって自然に語彙や文法などを習得することが難しい場合もあります。
言語発達を促すため、周囲の人たちのコミュニケーションに関心が持てるようサポートする、語彙や文法を身につける訓練をする、家族や学校と連携して環境を整えるなどの支援をします。
(4)摂食嚥下障害(せっしょくえんげしょうがい)
「摂食嚥下」とは食べて飲み込むことです。加齢や障害などが原因で、食べ物をスムーズに飲み込めない患者に対し、食事機能を維持するサポートをします。
摂食嚥下障害は特に高齢者に多く、歯の喪失・舌やあごの筋肉の衰え・脳卒中による麻痺などさまざまな原因が考えられます。
摂食嚥下障害を放置すると、栄養状態の悪化だけでなく、飲食物が誤って気管に入る「誤嚥(ごえん)」を引き起こしかねません。誤嚥によって肺炎になると、亡くなってしまう場合もあるため、摂食嚥下障害の対応は非常に大切です。
また、摂食嚥下障害が重度になると胃瘻となり、チューブによって栄養を摂取せざるを得なくなる場合があります。
言語聴覚士は、食事機能の維持・回復をサポートするとともに、その患者が摂食嚥下できる食事などのアドバイスもします。
(5)認知機能の障害
知覚・記憶・思考・感情など社会生活を送るうえで必要な機能を「認知機能」と呼びます。認知機能が低下する原因として代表的なのが、高次機能障害や認知症です。
言語聴覚士は、認知障害の評価やリハビリテーションを通して、社会生活を送れるようサポートします。
言語聴覚士は国家資格!目指すのにはどうしたらいいのかを解説
言語聴覚士は国家資格なので、国家試験に合格しなければなれません。
国家試験を受けるには、高校を卒業後、言語聴覚士養成課程を設けている大学・短期大学・養成校(3〜4年制)に進学し、既定のカリキュラムを修了する。または、一般の4年制大学を卒業後、養成課程のある大学・大学院の専攻科または養成校(2年制)を卒業する、どちらかを満たす必要があります。
2022年に行われた言語聴覚士の国家試験の合格率は、75%です。2022年に行われた他のリハビリテーション職の合格率は、理学療法士が79.6%、作業療法士が80.5%でした。過去数年間を見ると、言語聴覚士の合格率が最も低いケースが多いので、リハビリテーション職のなかでは難易度が高めといえるでしょう。
国家試験を受けるには、高校を卒業後、言語聴覚士養成課程を設けている大学・短期大学・養成校(3〜4年制)に進学し、既定のカリキュラムを修了する。または、一般の4年制大学を卒業後、養成課程のある大学・大学院の専攻科または養成校(2年制)を卒業する、どちらかを満たす必要があります。
2022年に行われた言語聴覚士の国家試験の合格率は、75%です。2022年に行われた他のリハビリテーション職の合格率は、理学療法士が79.6%、作業療法士が80.5%でした。過去数年間を見ると、言語聴覚士の合格率が最も低いケースが多いので、リハビリテーション職のなかでは難易度が高めといえるでしょう。
言語聴覚士を目指すなら知っておきたい!仕事のやりがいとは
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事といった、人が生活するうえで大切な機能の改善・維持をサポートする仕事です。
患者が少しずつ話せるようになったり、食べ物をスムーズに飲み込めるようになったりと機能を回復し社会復帰する過程を間近で見られるのは、大きな喜びです。「人の役に立ちたい」という思いを持つ人にとっては、やりがいと充実感を感じやすい仕事といえるでしょう。
また、障害など困難を抱える人の思いや生活を知ることで、大きな気づきを得る場合も少なくありません。
リハビリテーションの専門職として誇りを持ちながら、キャリアを築いていけるでしょう。
■まとめ
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事をするための機能を維持・改善する、リハビリテーションの専門家です。医療機関や介護施設などで活躍し、障害の検査や評価、機能訓練などのリハビリテーションに携わっています。
言語聴覚士になるには、所定のカリキュラムのある学校を修了し、国家試験に合格する必要があります。
患者が少しずつ話せるようになったり、食べ物をスムーズに飲み込めるようになったりと機能を回復し社会復帰する過程を間近で見られるのは、大きな喜びです。「人の役に立ちたい」という思いを持つ人にとっては、やりがいと充実感を感じやすい仕事といえるでしょう。
また、障害など困難を抱える人の思いや生活を知ることで、大きな気づきを得る場合も少なくありません。
リハビリテーションの専門職として誇りを持ちながら、キャリアを築いていけるでしょう。
■まとめ
言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事をするための機能を維持・改善する、リハビリテーションの専門家です。医療機関や介護施設などで活躍し、障害の検査や評価、機能訓練などのリハビリテーションに携わっています。
言語聴覚士になるには、所定のカリキュラムのある学校を修了し、国家試験に合格する必要があります。
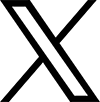
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
