病院で働く医師以外の仕事に転職!臨床外の転職先の選び方とは
2022/10/18
2025/04/14
日本国内の医師の9割以上が、臨床医として病院などの医療機関で活躍しています。しかし、医師免許や医師の経験を活かせるキャリアは、臨床だけではありません。
この記事では、病院で働く医師以外の転職先について解説します。これからのキャリアを考えるうえでぜひ参考にしてください。
この記事では、病院で働く医師以外の転職先について解説します。これからのキャリアを考えるうえでぜひ参考にしてください。
病院で働く医師以外の転職先とは?主な仕事を5つご紹介
医師が臨床医以外の仕事に転職する場合の主な仕事を5つご紹介します。
(1)産業医
産業医は、企業で働く労働者の心身の健康管理を行う仕事です。労働安全衛生法によって一定以上の規模の事業所では、産業医の選任が義務づけられています。
労働者の健康診断や指導、カウンセリングなどが主な仕事です。また、月に最低1回は職場を訪問して、労働環境に関するアドバイスや労働者への健康教育、職場内での健康被害の調査にも携わります。
産業医になるには、日本医師会認定産業医制度で規定された50時間以上の所定の研修を修了しなければいけません。
産業医はライフワークバランスがとりやすいのが特徴です。緊急の呼び出しや当直などがなく、週に3日以上休みが取れるケースが多いと言われています。平均年収は一般的な臨床医よりもやや低い、1200万円ほどです。
(2)介護老人保健施設
介護老人保健施設は、高齢者に介護と医療的ケアを行う施設です。介護老人施設には、必ず1名以上の常勤医師が在籍しなければなりません。さらに規模の大きい施設では、複数名の医師が勤務している場合もあります。
主な仕事内容は、入所者の健康管理や治療です。施設内では治療が難しい場合は、医療機関に入所者をつなぐ役割も担います。さまざまな体調の入所者を診療するため、幅広い診療科の知識や治療技術を要求される仕事です。施設によっては、緊急対応が必要な場合もあります。
平均的な臨床医よりも高年収を得られるケースが多く、年俸2000万円で働く医師も少なくありません。
(3)製薬会社のメディカルドクター
製薬会社の社員として、医学的な知見を活かし、臨床試験の計画書やプロトコールの作成、文献分析、有害事象の評価といった業務に携わります。主に、新薬開発や薬の安全性・有効性を審査する安全性部門と臨床医と製薬会社のパイプ役となるメディカルフェアーズの2部門で働きます。
これまで培った医学的知見にくわえ、製薬関連の新しい知識やスキルを身につける必要があるでしょう。治療が困難な病気の治療薬を世に送り出す、薬の副作用を軽減するといった点で、やりがいの大きな仕事です。
当直やオンコールなどがなく、在宅勤務やフレックスタイムを採用している製薬会社が多いため、ワークライフバランスの取れた働き方が可能です。年収は製薬会社ごとに異なりますが、ある程度の待遇が見込めるでしょう。
(4)公務員として働く
保健所をはじめとする公的機関にも、医師の活躍の場はあります。保健所長は例外をのぞいて、医師であることが必須条件なので、医師が公務員として働く場所として保健所が最も一般的です。
また、研究機関や省庁・都道府県庁などでも、医学的な知見を活かして研究や医療行政に従事しています。
勤務先によっては、医学の知識・スキルだけではなく法律知識など別ジャンルのスキルを要求される場合もあるでしょう。
公務員で働く場合、年収は700万円~1100万円ほどと一般的な臨床医よりも低めです。しかし、感染症・食中毒の発生といった緊急時以外は、ほぼ定時勤務で、ゆとりを持って働けます。また、福利厚生が充実しているのも公務員のメリットです。
(5)医療サービス事業会社
医療のIT化が進むのに伴い、医療用アプリやWebシステム、AIの開発といった分野で活躍する医師が増加しています。企業の社員として勤務する場合もあれば、医師本人が起業する場合もあります。
医学知識の他に、プログラミングなどのスキルが要求されるケースも多いので、ものづくりやデジタルが好きな医師に向いている転職先です。
給与は勤務先によって異なりますが、大きな利益を出せば莫大な収入を得られる可能性があります。
また、難易度が高めですが医学知識やコミュニケーション能力を活かして、コンサルティング会社で活躍する医師もいます。このように、医師の活躍の場は臨床以外にもたくさんあります。
(1)産業医
産業医は、企業で働く労働者の心身の健康管理を行う仕事です。労働安全衛生法によって一定以上の規模の事業所では、産業医の選任が義務づけられています。
労働者の健康診断や指導、カウンセリングなどが主な仕事です。また、月に最低1回は職場を訪問して、労働環境に関するアドバイスや労働者への健康教育、職場内での健康被害の調査にも携わります。
産業医になるには、日本医師会認定産業医制度で規定された50時間以上の所定の研修を修了しなければいけません。
産業医はライフワークバランスがとりやすいのが特徴です。緊急の呼び出しや当直などがなく、週に3日以上休みが取れるケースが多いと言われています。平均年収は一般的な臨床医よりもやや低い、1200万円ほどです。
(2)介護老人保健施設
介護老人保健施設は、高齢者に介護と医療的ケアを行う施設です。介護老人施設には、必ず1名以上の常勤医師が在籍しなければなりません。さらに規模の大きい施設では、複数名の医師が勤務している場合もあります。
主な仕事内容は、入所者の健康管理や治療です。施設内では治療が難しい場合は、医療機関に入所者をつなぐ役割も担います。さまざまな体調の入所者を診療するため、幅広い診療科の知識や治療技術を要求される仕事です。施設によっては、緊急対応が必要な場合もあります。
平均的な臨床医よりも高年収を得られるケースが多く、年俸2000万円で働く医師も少なくありません。
(3)製薬会社のメディカルドクター
製薬会社の社員として、医学的な知見を活かし、臨床試験の計画書やプロトコールの作成、文献分析、有害事象の評価といった業務に携わります。主に、新薬開発や薬の安全性・有効性を審査する安全性部門と臨床医と製薬会社のパイプ役となるメディカルフェアーズの2部門で働きます。
これまで培った医学的知見にくわえ、製薬関連の新しい知識やスキルを身につける必要があるでしょう。治療が困難な病気の治療薬を世に送り出す、薬の副作用を軽減するといった点で、やりがいの大きな仕事です。
当直やオンコールなどがなく、在宅勤務やフレックスタイムを採用している製薬会社が多いため、ワークライフバランスの取れた働き方が可能です。年収は製薬会社ごとに異なりますが、ある程度の待遇が見込めるでしょう。
(4)公務員として働く
保健所をはじめとする公的機関にも、医師の活躍の場はあります。保健所長は例外をのぞいて、医師であることが必須条件なので、医師が公務員として働く場所として保健所が最も一般的です。
また、研究機関や省庁・都道府県庁などでも、医学的な知見を活かして研究や医療行政に従事しています。
勤務先によっては、医学の知識・スキルだけではなく法律知識など別ジャンルのスキルを要求される場合もあるでしょう。
公務員で働く場合、年収は700万円~1100万円ほどと一般的な臨床医よりも低めです。しかし、感染症・食中毒の発生といった緊急時以外は、ほぼ定時勤務で、ゆとりを持って働けます。また、福利厚生が充実しているのも公務員のメリットです。
(5)医療サービス事業会社
医療のIT化が進むのに伴い、医療用アプリやWebシステム、AIの開発といった分野で活躍する医師が増加しています。企業の社員として勤務する場合もあれば、医師本人が起業する場合もあります。
医学知識の他に、プログラミングなどのスキルが要求されるケースも多いので、ものづくりやデジタルが好きな医師に向いている転職先です。
給与は勤務先によって異なりますが、大きな利益を出せば莫大な収入を得られる可能性があります。
また、難易度が高めですが医学知識やコミュニケーション能力を活かして、コンサルティング会社で活躍する医師もいます。このように、医師の活躍の場は臨床以外にもたくさんあります。
病院で働く医師以外の仕事に転職するメリット・デメリットとは
(1)メリット
医師が医療現場以外で働く場合、臨床医とは違うメリット・デメリットがあります。しっかり理解してキャリア選択することで、転職に成功する可能性が高まります。
一番のメリットとしては、当直やオンコールがないため勤務時間が安定しており、ワークライフバランスをとりやすい点があげられます。有給休暇も取得しやすく、家庭や趣味などプライベートと両立しやすいです。
さらに、医局など人間関係のしがらみが少ない、英語など医療以外のスキルを活かせるといった点も大きなメリットと言えるでしょう。
(2)デメリット
臨床の現場では医師がトップとして仕事をしますが、企業や行政で働く場合は上の方針に従って業務に取り組むことがほとんどです。臨床医ほど裁量が大きく、自由度は低いと言えるでしょう。
また、臨床に戻るのが大変、定年があるといった点もデメリットです。産業医など医療行為をする仕事以外に転職した場合、再び臨床医として働くのはハードルが高いです。また、企業や行政で働く場合は定年があります。
医師とは言え、定年後に再就職先を探すのは難しいので、定年後も長く働きたい場合は、臨床医を続ける方が選択肢は広がるかもしれません。
さらに、患者や家族に感謝されるといったやりがいを感じる機会が少ないなどのデメリットもあります。
医師が医療現場以外で働く場合、臨床医とは違うメリット・デメリットがあります。しっかり理解してキャリア選択することで、転職に成功する可能性が高まります。
一番のメリットとしては、当直やオンコールがないため勤務時間が安定しており、ワークライフバランスをとりやすい点があげられます。有給休暇も取得しやすく、家庭や趣味などプライベートと両立しやすいです。
さらに、医局など人間関係のしがらみが少ない、英語など医療以外のスキルを活かせるといった点も大きなメリットと言えるでしょう。
(2)デメリット
臨床の現場では医師がトップとして仕事をしますが、企業や行政で働く場合は上の方針に従って業務に取り組むことがほとんどです。臨床医ほど裁量が大きく、自由度は低いと言えるでしょう。
また、臨床に戻るのが大変、定年があるといった点もデメリットです。産業医など医療行為をする仕事以外に転職した場合、再び臨床医として働くのはハードルが高いです。また、企業や行政で働く場合は定年があります。
医師とは言え、定年後に再就職先を探すのは難しいので、定年後も長く働きたい場合は、臨床医を続ける方が選択肢は広がるかもしれません。
さらに、患者や家族に感謝されるといったやりがいを感じる機会が少ないなどのデメリットもあります。
病院で働く医師以外へ転職したい方へ!転職成功のコツとは
臨床医以外の仕事への転職を成功させるコツとして「副業から始める」「転職エージェントを活用する」があります。それぞれ解説します。
(1)副業から始める
最初から臨床以外の仕事へ完全にシフトするのではなく、副業としてスタートすることで、自分に合っているかを見極められます。
フリーランス医であれば、ゆとりのある働き方ができ、就業先の規定に反しなければ副業も可能です。臨床医としてのキャリアを保ちつつ、興味のある分野にチャレンジできます。
(2)転職エージェントを活用する
医師の9割以上が臨床医として働いているため、医師以外の仕事の実態がわからないという方も多いのではないでしょうか。
医療業界に特化した転職エージェントであれば、臨床医以外に転職する医師のサポート経験が豊富なため、的確なアドバイスがもらえます。
また、ワークライフバランスのとりやすい医療機関への転職など、臨床医を続けながら希望の働き方ができるよう提案してもらえる可能性もあります。
いざ転職する場合も、応募先とのやり取りや書類作成、条件交渉など手厚いサポートをしてもらえるので、上手に活用するのをおすすめします。
(1)副業から始める
最初から臨床以外の仕事へ完全にシフトするのではなく、副業としてスタートすることで、自分に合っているかを見極められます。
フリーランス医であれば、ゆとりのある働き方ができ、就業先の規定に反しなければ副業も可能です。臨床医としてのキャリアを保ちつつ、興味のある分野にチャレンジできます。
(2)転職エージェントを活用する
医師の9割以上が臨床医として働いているため、医師以外の仕事の実態がわからないという方も多いのではないでしょうか。
医療業界に特化した転職エージェントであれば、臨床医以外に転職する医師のサポート経験が豊富なため、的確なアドバイスがもらえます。
また、ワークライフバランスのとりやすい医療機関への転職など、臨床医を続けながら希望の働き方ができるよう提案してもらえる可能性もあります。
いざ転職する場合も、応募先とのやり取りや書類作成、条件交渉など手厚いサポートをしてもらえるので、上手に活用するのをおすすめします。
まとめ
医師が臨床医以外に転職する場合、産業医や介護老人保健施設、製薬会社など選択肢はたくさんあります。
臨床医以外への転職には、ワークライフバランスがとりやすいといったメリットがある反面、臨床医に戻りにくいなどデメリットもあります。
転職を成功させるには、まずは副業としてスタートする、医療業界専門の転職エージェントを活用するといった方法が有効です。
医療業界に特化した求人サイトでは、医師のキャリアについて解説したコラム記事が記載されている場合があるので、まずは情報収集からスタートするのもおすすめです。
臨床医以外への転職には、ワークライフバランスがとりやすいといったメリットがある反面、臨床医に戻りにくいなどデメリットもあります。
転職を成功させるには、まずは副業としてスタートする、医療業界専門の転職エージェントを活用するといった方法が有効です。
医療業界に特化した求人サイトでは、医師のキャリアについて解説したコラム記事が記載されている場合があるので、まずは情報収集からスタートするのもおすすめです。
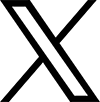
この記事が気に入った場合は
Xへポストをお願いします
